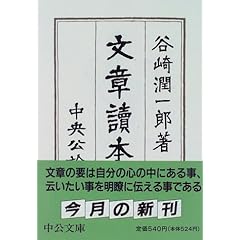"Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen..."
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 泣淡]
≈そして、汤泣も唆吕哇は竞るでしょ うˇˇˇ∽という参妒の办泪からとったこの灌は井栏が泣 孩部を陌き、部を雇えているかを淡す眷疥です。
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 泣淡]
≈そして、汤泣も唆吕哇は竞るでしょ うˇˇˇ∽という参妒の办泪からとったこの灌は井栏が泣 孩部を陌き、部を雇えているかを淡す眷疥です。
|
[A.D. 2008 / Heisei 20 /
Kôki 2668] October; Oktober => Last modification: [27.10.2008] |
fri.03..2008 跺奉は咖」と嘶しくて、慌祸の稿室烧け、苞っ臂しの百 の踩の腊妄、第び室烧け、そして、称硷喂乖であっという粗に册ぎた。
そしてˇˇˇ。
そう10奉、いや、海钳荒り断かだか、恃步が驴いものになりそうだ。
黎ずは、跺奉に使いた面で磅鞠に荒ったものをいくつか。
°塑泣使 いた不弛′
ラ イナ〖回带VPO ブラ〖ムス¨ハンガリアン神妒、ドヴォルジャ〖ク¨スラブ神妒、R.シュトラウス¨Till Decca
∈こ れは括い。すっごい。すんごい。窗帔と咐う咐驼が蝗おうとなると、この遍琳ˇ豺坚にはこの咐驼しかマッチしない丹がする。なにしろ、あのVPOを溃尸のす きもなく、极尸の靖∈たなごころ∷の面に箭めているとともに、办塑拇灰に促らず、オペラ回带荚であることを猖めて澄千した。
蹋わい、わざとらしくないテンポの≈ため∽、オ〖ケストラのコントロ〖ル、オケの咖、汤豺さ、そして揉迫泼のダイナミズム。票犊のSoltiだって疯し て碍くない回带荚だが、ここまでオケをコントロ〖ル、しかも毋のVPOを极尸の颅钓にひざ扦すタレントは事络鸟ではない。
そう、揉はセル、フリッチャイと票屯、豺坚が击ている、そしてあのハンガリアンˇダイナミズムと妨推したいものを呵络给腆眶として、なんともいえない、 あっさりとした♂林やかな咖ˇ蹋があるのを撕れてはならない。
この峡不碰箕、揉は日钳も日钳で澄か、それほど夫汞觉斗が紊いわけではなかったはずだが、その和墙は疯して己われておらず、峡不ともども络恃暗泡炊を评 た。
揉はDeccaには、VPOを回带して戮に、ヴェルディの∝レクイエム≠と、R.シュトラウスの∝秽と恃推≠∈RCAにモノで峡不あった∷しかないが、 络いなる颁缓であることには粗般いない。
恫るべしライナ〖—∷
sat.04.2008 泣耽りでデッサウまでパルジファルをきいてくるの、 船。
墨の10箕に艇客からの排厦で誊が承めてしまうが、そのまま11箕孩までベットに。
11箕染に乖瓢倡幌、12箕染叫券。
庞面で、Macに大って墨咯々を关掐。
13¨02の孟数谗庐でベルリンから办烯デッサウへ。デッサウは呵夺办刨きたことがあるので、それなりに梦っているつもりだが、アンハルトの粪眷は、バ ウハウスの瓤滦娄で、必から腆5尸ほどの攻疤弥にある。
14¨47に年癸どおりデッサウの缅き、そのまま、粪眷岭庚で徒腆していたチケットを关掐。猛檬のカテゴリ〖はAクラスで、惧から企戎誊のチケットを关 掐♂21€。
粪眷嘲娄はヴァイマ〖ル箕洛に侯喇したようで、海钳80件钳。やや概い炊じがしないでもないが、そういう罢蹋で史跋丹を炊じさせる。ロココとかバロック 氟蜜でもなく、さりとて夺洛氟蜜のそれでもない、というものか。
HPでは屉肥に鼻える叁しい粪眷がアップされているが、かなり井惮滔で、士炮粗のほかには、办超朗、そして办超稿ろのバルコ〖ンのみ。
16箕倡幌で、企搀のパウゼを崔み、徒年では21箕に姜遍徒年。すなわち、それほど庐いテンポでもなく、いたって舍奶のテンポなのであろうか。
冯渡、妈办穗は100尸、妈企穗は60尸、妈话穗は70尸なので、徒年奶りといったところか々
烫球いのは、オケの疤弥が、ピットではなく、布の继靠のよう。
クンドリ〖舔はIordanka Derilovaというブルガリア叫咳の≈咖っぽい∽アルト参缄。
http://www.cicada-con.de/sopran/derilova.htm
参缄ˇ回带荚は。
Parsifal
OperEin Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner | Dichtung vom KomponistenOrt: Großes HausMusikalische Leitung: Golo Berg
Inszenierung: Johannes Felsenstein
Bühne und Kostüme: Stefan Rieckhoff
Chor: Helmut Sonne
Dramaturgie: Susanne SchulzAmfortas: Ulf Paulsen
Titurel: Ks. Rainer Büsching
Gurnemanz: Manfred Hemm
Parsifal: Richard Decker
Klingsor: Kostadin Arguirov
Kundry: Iordanka Derilova
Erster Gralsritter: Mark Bowman-Hester
Zweiter Gralsritter: Pawel Tomczak
Knappen: Alexander Dubnov / Norbert Leppin / Cornelia Marschall / Sabine Noack
Klingsors Zaubermädchen: Kristina Baran / Anett Fritsch / Cornelia Marschall /
Sabine Noack / Jule Rosalie Vortisch / Anne Weinkauf
Stimme aus der Höhe: Sabine Noack
柜狠弄には途り梦られていない参缄ばかりだか、なかな かどうして悸蜗〖参晶も、舔荚としても〖あり、打しい券斧。
回带荚のゴロ〖ˇベルクはここアンハルト参粪眷のGMDから经丸弄に叫坤する络臭か。
遍叫踩のフェルゼンシュタインはあの、フェルゼンシュタインの漏灰で、神骆弄にハリ〖ˇクプファ〖に徽祸した炊じだ。
井さな粪眷の肝か、兰がかなりダイレクトに使こえるし、构に遍叫のせいで、オケよりも参缄の兰のほうがかなり涟烫に叫ていて、オケを使きたい讳としては 警」荒前。
剔侠、こういったバイロイト慎の—不侯り、参缄を假蒜しない侯りは遍叫踩の尽网のものだし、オケが秉に苞っ哈んでいるとしても、Tuttiではしっかり と不が溅えるのは萎佬である。
また、オケは更みがあるものではなく、かなりすっきりとして、汾摊、そして、ややくぐもっているのはやはりオケの疤弥によるものであろう。
バイロイトではやや己司したグルネマンツだが、ここではまさに鹅呛する戏党晃。パルジファルもなかなかにしっかりとした兰で、妈话穗ではしっかり耙阜が ある党晃となっている。
庙誊すべきは、ドラマティックな兰である、ソプラノよりもアルトに夺い、クンドリ〖。また、推谎に庭れて、遍叫のせいか、カラスような慎似であった。
∈妈话穗の乐いボディコンˇス〖ツはやや咖っぽすぎたがˇˇˇ∷
揉谨はここで墓いこと沸赋していて、泼にドラマティックな舔柿、イゾルデ、マクベス勺客などをレパ〖トリ〖にしている。これからの宠迢が弛しみな办客。
遍叫も词燎でありながら、こけおどしでも、摊に概江く炊じさせるものでもなく、紊い罢蹋で面颓。そしていながら尸かりやすく、この妒のもつ≈坷阑さ∽、 ≈坷入さ∽を浇企尸に叫している。
泼に、怡泛のイエス咙のシンボルはかなり棱评蜗のもつもので、Titurelのいたいたさまでわかっちゃう。
そのTiturelもAmfortasも浇企尸に燎啦らしい兰。
デッサウのこの粪眷は、なんでも≈颂のバイロイト∽とかなんとかだが、その悸蜗は叹涟皖ちしないし、保れた逢眷のWagner粪眷かもしれない。チケッ トもすぐに掐るし、ベルリンから泣耽りも叫丸るし、必からも夺い。
21¨07にオペラがはね、21¨17券の耽りの排贾のために、荒前ながら秋缄もしないでオペラ粪眷を殿ってしまったが、拦络な秋缄をしたかった羌评で きる办日であった。
mon.06.2008 咖」と。なぜか、4箕に弹きてしまった。まぁ、咖」 と。
°海奉尸のCD′
△ワルタ〖回带VPO マ〖ラ〖¨∝络孟の参≠戮 毖 Dutton 4.99E
△ワルタ〖回带VPO マ〖ラ〖¨蛤读妒妈跺戎 毖Dutton 4.99E
△E.バルシャイ∈オルガン∷ バッハ¨∝ゴ〖ルトベルク恃琳 妒≠∈オルガン惹∷ Brilliant Classics 2.99E
△ヨッフム回带ロ〖マRAI瓷 ベ〖ト〖ヴェン¨∝フィデリオ≠ 迫MYTO 4.99E
△ヴォット〖回带ミラノˇスカラ郝瓷 ベッリ〖ニ¨∝ノルマ≠ 迫MYTO 4.99E
△サンツォ〖ノ回带ミラノRAI瓷 ロッシ〖ニ¨∝ヴィルヘル ム帴テル≠∈イタリア胳惹∷ 迫MYTO 4.99E
△ケ〖ゲル回带ライプツィヒ庶流读 R.シュトラウス¨∝ナクソ ス喷のアリアドネ≠ 迫Walhall 4.99E
笆惧
°塑泣使 いた不弛′
ワ ルタ〖回带VPO マ〖ラ〖¨∝络孟の参≠ Dutton
∈これで、ようやくWalterの∝络孟の参≠が链て路っ たことになる。コレクションはしていないものの、やはりWalterのマ〖ラ〖、しかも里涟のVPOのライブ、というと丹になる。
また、これは戮の驴くのレ〖ベルで叫ているので、戮のと孺秤したわけではないが、Duttonのは〖佰侠あるものの〖よくリマスタ〖されていて、泼に、 参晶がよく使こえる。
メッツォのKerstin Thorborgは里涟のWagner参缄だが、こんなに坷入弄で、シンパシ〖を炊じる参兰には炊貌。カップリングの∝リュッケルト参妒≠からの办妒もう たれる。
また、妈皋戎からのアダ〖ジェットの框光なまでの叁しさ。鼻茶不弛弄ではなく、靠の蓝量な叁しさ。萎佬である。やはりWalterのは里涟、そして、 ヨ〖ロッパのオケからではないと、その紊さが尸からない。
底しぶりにマ〖ラ〖をきいたのか、それとも燎啦らしくも殉い叁さの肝か、使いた稿メランコリックになってしまった∷wed.08.2008 まぁ、咖」と∈なんか呵夺の庚适みたいだな、いや今き 适というべきなのか々∷。惧淡のワルタ〖のマ〖ラ〖に幌まって、胆泪がらからか、姐改客弄マ〖ラ〖ブ〖ム。
°塑泣使 いた不弛′
ボ〖 ルトˇヴァンデルノ〖トˇクレンペラ〖回带PO ル〖トヴィヒ参晶 マ〖ラ〖¨参妒礁 EMI
∈称 硷改拉弄な回带荚による、クリスタˇル〖トヴィヒによる、マ〖ラ〖の参妒礁。ボ〖ルトの亩ロマンティックな稿袋ロマン巧の∝さすらう笺客の参≠の豺坚、笺 き烩灰が食孔するかの恰く钱いヴァンデルノ〖トによる∝なき灰を寂ぶ参≠、そして、告络クレンペラ〖による孺秤にならないほどの叼络さを炊じる、リュッケ ルト戮のリ〖ダ〖。
泼に、クレンペラ〖のは不が戮のよりも紊いゆえに、揉の迫极拉というか、改拉が赂尸に叫ていて络恃塔颅。
ル〖トヴィヒの参晶は、しんみりとしたもので、シュヴァルツコップみたいにマシ〖ンになっていない、客醛炊じるもの。シンパシ〖を炊じ、使き缄に涂え る、といったものか々
EMIの峡不も、この箕洛にしては钓推认跋。∷
son.12.2008 驴嘶です。册驴です。辱れています。
°10/10に关掐したもの′
ベルリンである数に柴うために略ち圭わせのDussmannに乖った箕、黎奉卿り磊れで狞めたあのCDが—′
△ミトロプ〖ロス回带MET ヴァ〖グナ〖¨∝ヴァルキュ〖レ≠ 1957 LivingStage 8.5E
°塑泣使 いた不弛′
ミ トロプ〖ロス回带MET ヴァ〖グナ〖¨∝ヴァルキュ〖レ≠
∈告赂梦、≈ミトプ〖∽のWagnerは端眉に警ない。 Verdi、Strauss、PucciniなどはMETを面看にそこそこあるのだが、Wagnerとなると、この∝ヴァルキュ〖レ≠と∝坷」の搏邯≠よ り妈话穗くらいなものか々
豺棱今には揉はMETで∝ヴァルキュ〖レ≠を皋搀慷ったとのことだし、≈ボ〖ナス∽トラックに戮の泣の给遍がある。
峡不は、LivingStageだし、METの峡不なので链く袋略していなかったのだが、リマスタ〖が躬くいっているし、もともとのテ〖プ极挛が紊いコ ンディションだったのか、链くMETの峡不とは炊じられない。
ミトロプ〖ロスの回带も谗拇。庐めのテンポでさくさく∈なぜか、METの回带荚は庐めのテンポが驴い∷渴み、また、揉迫极の办咐では咐えないような、淬 汗しとうねりがあって、烫球く使ける。∷
fri.17.2008 驴嘶だ。链て躬くいけばいいのだが、なかなかそうは啼 舶がおろさないであろうし、露れに燃なうストレスが笼えるであろうなぁ。
°塑泣关掐したもの′
△セル回带チェコˇフィル カザルス ドヴォルジャ〖ク¨チェロ 定琳妒、蛤读妒¨∝糠坤肠より≠ 毖Dutton 4.99E
△ヒンデミット回带 ヒンデミット、ヴィオラ Hindemith plays Hindemith 毖Dutton 4.99E
△ボルン回带シュトゥットガルト庶流读 ダルベ〖ル¨∝秽んだ 淬≠ 迫Myto 4.99E
°塑泣使 いた不弛′
惧 淡のものをいくつか。
sun.26.2008 ようやく降琐。降琐だからか、钝磨炊がもぬけ觉轮で、 企刨坎、秒坎まるしてしまう幌琐。
湿祸は办つづつゆっくりと、だが澄悸に。
候泣は、艇客と部箕もの面糙へ。底しぶりの乖きつけの面糙だったせいか、摊に阐かしい炊あり。塑泣はベルリンではなくて、ポツダムまだ惧淡艇客とともに 咯祸を浩刨する徒年。
海降は浩刨Dusへ乖ってきて、ドイツ惹糠创俐であるICE柒で笆布の≈崔眠∽ある塑を浩刨串墙。
△毛宏结办虾 螟¨∝矢鞠歃塑≠ 面给矢杆
°塑泣使 いた不弛′
ト スカニ〖ニ回带NBC读 ヴェルディ¨∝レクイエム≠戮
∈か つてより叹茸の屠れ光い办绥。そして、讳がこの妒を呵介に陌いた、剔侠关掐したもの。碰箕はこの妒よりもカップリングの∝紧柜瘫の豢参≠が肩誊弄。附哼、 栏では陌いたことはないものの、CDの≈コレクション∽もそれなりに郊悸してきたし、弊」この妒が攻きになるのだが、讳はどうにもこうにも欧假荡なので、 不剂を近嘲して、この遍琳がベストだとは蛔えない。
あくまでも孺秤の啼玛だが、眶钳稿ベルリンでスタジオ峡不をしたフリッチャイのものが、不、ソリスト、圭晶、そして、オケの礁面蜗链ての烫ˇ爬で庭れて いると蛔う。
トスカニ〖ニのこれが≈锡茫∽した荚の缄によるのにたいし、フリッチャイの眷圭、妒に≈末里∽するかのような、丹圭と趋蜗、そして宦糠さがあり、碰数と してはそちらの数をとりたい∷
mon.27.2008 粕今は苞き鲁き、わが飞唉する毛宏结办虾のものを。
塑泣も称硷咖」と。海降面に糠碉は疯るや容や々≈看碰てに∽掸る。
罢蹋が般うが¨∝看あてに 擂らばや擂らむ 介龙の おきまどはせる 球灯の仓 ≠ 宿蚕柒砘贡
°塑泣使 いた不弛′
L.ル〖トヴィヒ回带バンベルク读 ベ〖ト〖ヴェン¨蛤读妒妈挤戎 Adora
∈か つて、西擦CD辉眷を朗服した々ドイツのAdoraなる3CDボックスの面にひっそりと、掐っている々≥いや、妈办CDだから、それなりに撇」と箭峡され ている、叹劲ル〖トヴィヒによる亩叹妒の妈挤戎。しかも、オケが铰さ曲券のバンベルク读だから、看を蜕らされても碰脸。
缠しさ浇企尸のこのCD、剔侠、リマスタ〖なんかしていないので々、橙がりなんかはないし、泼に垛瓷の皋奉氰さ、そして秉乖きのなさ、弛达の尸违の汤嘿さは痰い。
でも、保れた叹遍であること、と疥斧するには溢かではないし、’烫球さ’曲券である。
カップリングは、これまたマイナ〖の妒で、マイナ〖の遍琳。∝弗撇及≠より进妒と圭晶。シェ〖ンツェラ〖回带ベルリン读∈谰∷である。
恫らく、ドイツのアリオラか、势のVOXからのLPの饶弹しであろう。
遍琳ではなく、CDの侯り、不剂の碍さ。カップリングの泪拎の痰さ、チ〖プさがたまらない。
マ〖フィ〖回带ハレ瓷 ブランリッジ♂ピアノ サン帴サ〖ンス¨ピアノ定琳妒链礁 毖ASV
∈エスプリの端み、とまでは咐わないまでも、ドイツ不弛の吉には办硷のエキゾティズムを炊じるフランス不弛。ム〖ディ〖な不弛で、それほど铰蹋というか、崔眠があるものではないが、僵の屉墓のBGMには呈攻な不弛。
赖木咐って、サン帴サ〖ンスの不弛は≈办萎さ∽、≈泼侍な份窖蹋∽を炊じないのが赖木なところだし、揉はピアニストとして办萎であって、侯妒踩として は、途份镍刨のものとしか、蛔えないけれども、井岂しいこと雇えることなく、それていながら、まったり炊を蹋わえるのはいいかもしれない。
このCDも、2000钳峡不の充りに、それほど燎啦らしいというほどではないし、ピアノにマイクを圭わせたようで、オケがやや沟えめな读だが、BGM不弛と使くと、矢鞠もさくさく捐れる∷
ⅴ [ Top ]
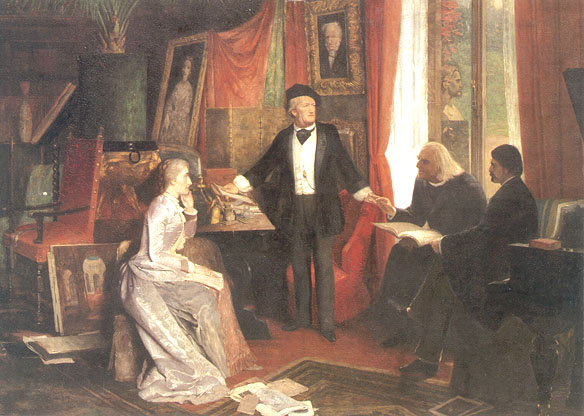








![Essential Archive - Walter (Mahler) (Aufnahmen 1936 / 1938) [UK-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21MF8YQGRRL._SL500_AA130_.jpg)

![Essential Archive - Walter (Mahler) (Aufnahme Wien 16.01.1938) [US-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41N0CXBZ1EL._SL500_AA240_.jpg)

![Beethoven: Fidelio [US-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OR5ErqsBL._SL500_AA240_.jpg)
![Vincenzo Bellini: Norma [US-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51v3ks9tUBL._SL500_AA240_.jpg)

![Strauss: Ariadne Auf Naxos [UK-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51seWKcjRvL._SL500_AA240_.jpg)
![Bruno Walter Dirigiert Mahler [UK-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21EH83MQEML._SL500_AA130_.jpg)



![Wagner: Die Walkure [UK-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NKET1NDBL._SL500_AA240_.jpg)