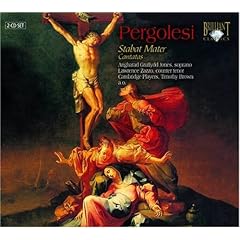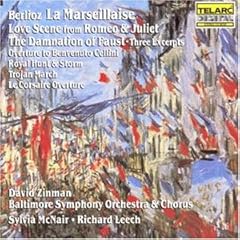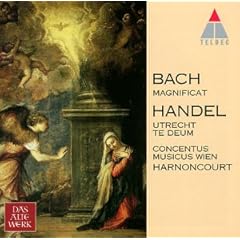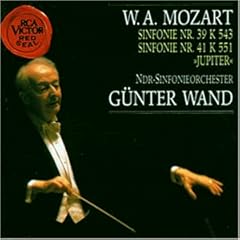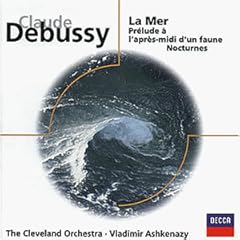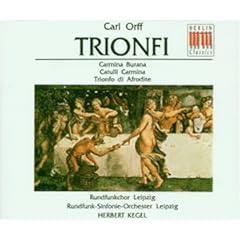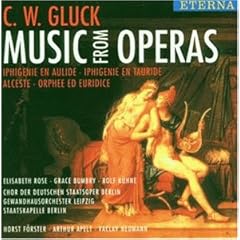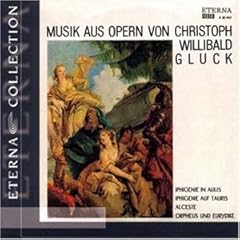"Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen..."
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょう・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょう・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
|
[A.D. 2007 / Heisei 19 /
Kôki 2667] June; Juni [Last modification: 24.Jun.2007] |
son.03.06. 六月ねぇ。早いもので、今年もあとわずか・・・でなく、半分過ぎてしまう、のか。
日本でも雨季が近いようだが、こちらでもなんともいえない、気持ち悪い雨季のような、湿度が高い日々が多い。やっぱり、異常気象だよ、こりゃ。
<本日聞いた音楽>
ラインスドルフ指揮ボストン響 ベートーヴェン:交響曲 RCA
[尚、この全集はいま廃盤らしい。Amazonでヒットしなかった。]
(60年代なのに、この明確な指揮!やはり、流石良い耳を持っていたラインスドルフだけある。少々もわーっとしている所も無きにしも非ずだが、なかなかの 全集である。全集という形式ではヴァントのそれが似たような解釈をとっている。レイボヴィッツもそうだが、あれは少々エキセントリックな感じが。ドイツも の、という感じはだからしないので、有る意味「中性的」に聞こえるのかもしれない。)
mon.04.06. 寒い。涼しい。でも、日課の散歩を敢行。一時間以上歩いたかな?少々、気が滅入っているので、こういうのは良いかもしれない。
<今月購入したCD>
@ガーディナー指揮EBS ハイドン:『天地創造』 独Archiv 12.99E
@ブラウン他 ペルゴレージ:合唱曲集 蘭Brilliant Classics 3.99E
@ジンマン指揮 ボルチモア響 ベルリオーズ:管弦楽曲集 米Telarc 7.99E
@アーノンクール指揮 CMW バッハ、ヘンデル 独Teldec 4.99E
@ベーム指揮 VPO モーツァルト:『イドメネーオ』 独Walhall 4.99E
@エレーデ指揮 バイエルン放送響 ヴェルディ:『仮面舞踏会』(ドイツ語版) 独Walhall 4.99E
<本日聞 いた音楽>
ガーディナー指揮EBS ハイドン:『天地創造』 独Archiv
(少々期待していたよりも、「大人しめ」で残念。もっと、ドライで、がんがんになるハイドンだろうと予想していたのだが。合唱の素晴らしさは言わずもがなだが、これ、様々な意味で録音レヴェルがおかしいのでは?)
mon.18.06. 久しぶりの更新ー相変わらずの横着になってきたゆえ。野暮用で先週末は久々にDresdenへ行く。相変わらずの旧東独の建築様式、和洋折衷ならぬ、新旧 混在の景観は宜しくない。Frauenkircheは再建なったがーようやくーやや、観光地観光地していたり(ま、それしかないのだが)、少々距離を置い てみたのでそれほど感銘はせず(中へもはいっておらず)。
それにしても、暑かった。更に蒸し暑い。これにはたまげる。
いつでも、観光客は観光客であったのだ。
<本日聞いた音楽>
ヴァント指揮NDR響 モーツァルト:交響曲 41番 RCA
(曲も曲だし、演奏も演奏。まったくもって見事な出来。完璧。アーティキュレーション、進行、内声部の響かせ方、適度な緊張感と柔らかさ。第四楽章でのフーガの捌き方に思わず暑くなってしまった。新たな発見が多く気がついた、「あるべき」演奏・解釈であった。)
アシュケナージ指揮クリーブランド管 ドビュッシー:『前奏曲』、『夜想曲』、『海』他 Decca
(Debussy やらR.シュトラウスやらの管弦楽曲はやはり、どうしても巧いオケで聞かなければならないし、聞きたい。だが、「巧い」、だけではなくて、「雰囲気」もな いとたんなる「オケのための練習曲」になってしまう。そのライン・バランスが大切である、と思う。クリーブランドは言うまでもなく「巧い」オケなのは既に 実証済みだし、アシュケナージも過不足なく捌くのは良い。これは、雰囲気よりも、「技術」にやや傾斜気味な演奏だが、録音が例によって素晴らしいリマス ターだし、なかなか好感のもてるものだ。
sam.23.06. 最近は、雨が降ったりやんだりで、しかも、急激に降ってきたと思ってらやんで、それで再びからっと晴れる、というわけ分からん天候が続いている。
昨今、「民度」と言う言葉をよく見る。
| 大辞泉 |だと生活及び、経済・文明の程度、| 大辞林 | だと生活・文化水準の程度となっている。そのほかの辞書は、あるサイトを孫引きしてしまうが・・・
『三省堂国語辞典』
■国民の文明・生活の程度。「民度が低い」
『新明解国語辞典』
■その地域に住んでいる人びとの経済力や文化の程度。
『新潮現代国語辞典』
■国民・住民の経済生活・文化文明の程度
『岩波国語辞典』
■人民の生活程度「民度が低い」
『明鏡国語辞典』
■国民・住民の生活水準や文化水準の程度。「民度が高い」
となっている。ようは国民若しくは文明のレヴェルだが、大体においてみるのは「。。。が低い」(日本の場合は特に、中国・韓国を指している)であって、その他の要素は無視している。
正直言って、両国は「或る意味」レヴェルが低いが、日本も他国(特にこの場合には欧米諸国)と比して決して同等、高いわけではない。勿論、日本の良い部分も或る程度はしっているのだが・・・。
しかし、先進国と日本では喧伝されている、ドイツもなかなかにして良いとは思えない。当然のことながら、日本に行く、報道されているドイツに関するもの はフィルターがかかっているので、その「真実」−この場合にはドイツの真実ーを示している訳ではない。こういうと妙だが、ドイツという国にくるまではその フィルターに騙されていたので、メディアの低能の罪悪は大きいと言わざるを得ない。
とはいっても、どの国へいっても、その問題があるわけで、「地上には楽園はない」、若しくは「住めば都」なのである。
生きなければ、ならないのである。
<本日聞いた音楽>
ケーゲル指揮ライプツィヒ放送響 オルフ:『勝利三部作』 独Berlin Classics
(久 しぶりのオルフ、久しぶりのケーゲルである。こういったからっとしない天気には「元気一発」こういったどっかんとしてものを聞くのが宜しい。相変わらずの 精密さ、ダイナミズムさ、のりのよさで、比較盤はライトナーのしかしらないけれど、録音も含めて、これは先ず第一にお勧めできるものであろうか?旧東のオ ケで制約があったとはいえ、ケーゲルの現代音楽に対する率先性、包容力のお陰で、「一歩すすんで」こういった音楽を楽しめるのは偉とすべきであろう。)
フェルスター、アーペルト、ノイマン指揮GOL他 グルック:音楽集 独Berlin Classics
(BerlinClassics づいて、お次は実にしぶーい:このレーベルにぴったりの言葉だ、を聞く。頑固一徹で、「ドイツ音楽」としてグルックを一生懸命に捌いている。この、ひたむ きな一生懸命さが好きだ。軽くなく、不真面目ではなく、表面的ではなく、音楽一筋のもの。)
(いつも右の写真しかしらないので、右のも追加しておく。)
(左は指揮者のフェルスターさん、まだご存命だそう。渋い!お隣は御存知ノイマンさん。チェコのラジオ局から借用。尚、B.C.にはかなりのノイマンの録 音があるから、是非例のBOXシリーズで出して欲しい。グルック、ハイドン、マーラー、ブルックナー、ベートーヴェン、スメタナ、ドヴォルジャーク、 ヴァーグナー、R.シュトラウスあたりか?)
▲ [ Top ]