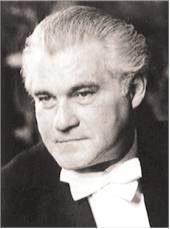"Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen..."
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょう・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょう・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
|
[A.D. 2005 / Heisei 17 / Kigen 2665] November; Novembre [Last modification: 30.Nov.2005] |
mit.02.nov.
今年も後残り僅か。ラストスパートに向けて後ひとふんばり。
mit.02.nov. <本日購入した CD>
@ フルトヴェングラー指揮BPO ベートーヴェン:交響曲第九番『合唱つき』 独Archipel 3.99E
(総統閣下誕生日前夜でのコンサート)
@E.クライバー指揮ACO+LPO+VPO ベートーヴェン:交響曲第3+5+6+7+9番 独Andromeda 3CD 6.99E
(全てDecca録音のもので、リマスター したもの。)
@ジュリーニ他指揮LPO+NPO ベートーヴェン:『ミサ・ソレムニス』、ミサ曲ハ長調、『オリーブ山上のキリスト』 Brilliant Classics 3CD 5.99E
(『...キリスト』の方はヘンスラー原盤 のリリング指揮のもので、既に所有していた。)
@ローター指揮ベルリン帝国放送管 フンパーディンク:『ヘンゼルとグレーテル』 独Walhall 3.99E
(カップリングはアーベントロート指揮 GOLの『ムーア人狂詩曲』)
@クレンペラー指揮PO モーツァルト:『魔笛』 EMI 9.99E
@フリッチャイ指揮RIAS管 J.シュトラウス:ガラ・コンサート 独Gebhardt 5.99E
@フリッチャイ指揮ベルリン市立オペラ管 ヴェルディ:『ドン・カルロ』(ドイツ語版全曲) 独Walhall 6.99E
(かつてCantusで持っていたが、余り に酷い録音なので実家に戻した。)
@ケンペ指揮MET ヴァーグナー:『トリスタンとイゾルデ』 独Walhall 6.99E
@ヨッフム指揮バイエルン国立管 ヴァーグナー:『マイスタージンガー』 独Walhall 9.99E
(Orfeoと同じ録音。しかし、ボーナス が!)
@カイルベルト指揮バイロイト祝祭管 ヴァーグナー:『ヴァルキューレ』1954年 独Archipel 6.99E
(カイルベルト三度目の『ヴァルキューレ』 でこの年の録音はこれしか残っていない。)
@クナッパーツブッシュ指揮バイロイト祝祭管 ヴァーグナー:『パルジファル』 1954年 独Archipel 9.99E
(バイロイト実況の三度目のもの)
@クレンペラー指揮NPO ヴァーグナー:『さまよえるオランダ人』(ドレスデン版?) EMI 9.99E
以上
(本当はこんなに買う予定は無かったのだが、店員にクリスマスセールだから、79Euro以上買うと10Euroボーナスつくよ、といわれたので、こうな りゃ引き下がるわけには行かない。結局82Euro程買ってしまったが、やはりボーナス券には換え難い。)
<本日聞いた音楽>
先ずは総統閣下の誕生日 イブ祝祭コンサートの模様を、恐らくラジオで録音したであろう、未公開ライブの模様を。この異様なライブを聴いていて、形容しがたい思いをはせるのは私だ けではないはず。この模様は既にTVで最終部のコーダだけ見たが、ナチのお歴々の面前で猛烈な指揮振りをしているフルトヴェングラーと、終演後の「ご挨 拶」の醒めた指揮者と感激した趣のご歴々のコントラストが悲壮であったし、人類愛を謳ったはずのシラーの歌と現実に起こっているなんともアイロニックな ギャップが音楽という一つの事象を超えて、現実の政治を考えざるを得なかった。音楽や演奏はともかくも、その裏に潜む歴史の恐ろしさを考えざるを得ない記 録である。
お次は、フリッチャイ指 揮のJ.シュトラウス・ガラ・コンサートの模様を。ボーナスにはP.アンダースのオペレッタの抜粋より。シュトラウスのヴァルツなどは実際問題として演奏 するというか、解釈をして観客を芸術レヴェルにまでに納得させるのは実は至難の業だとは思うが、ここに演奏されているフリッチャイを始めとして、E.クラ イバー、クナッパーツブッシュ、一部のケンペの録音でのみ、私はシュトラウスの芸術性を感じさせられた。もっとも、これらは一般受けは必ずしもしないであ ろうが、その完成された孤高の芸術作品としてのシュトラウスを堪能するのにはやはり、こういった大指揮者の出番であろう。尚、DGでの録音でも感じたのだ が、ベルリンのそれはスコアが違うようで、オリジナルではなく改編してある。
クナといえば、パルジ ファル。パルジファルといえばクナ。定番だが、さて数多い彼の同曲の演奏ではどれを選ぶかが問題だ。勿論、どれも素晴らしいし、一番を選ぶ必要もないし、 またまた彼以外にも素晴らしい演奏をする指揮者がいるのは確か。この1954年の実況盤はその中でも極めて高度に昇華されたものらしい。確かに、第一幕の 前奏曲からただものではない、神秘性と共感が嫌が応にも感じることが出来た。テンポは通常のKnaよりも更に遅いが、その見通しの良さから、窮屈だったり 偏屈だったり、異様だとは決して感じない。第一幕だけだが、AmfortasをHotterが歌い、GurnemanzをGreindlが歌っている。こ れ逆だろうに。でも、まぁ、良いか。残りは翌日以降にでも。
fre.04.nov. なんか、最近天候の変化が激しくて、体調も万全とは言いがたい。本朝は例によって頭痛で起こされる。薬はこのまないのだが、万難を帰して、念の為に Aspirinを服用。結構すぐに効きますね。ただ、やはり、少々たるーくなったり、眠くなったりするのは仕方ないか。
ほんと、はっきりしない気候。廻りも、アナウンサーも鼻声、風邪声です。
<本日聞いた音楽>
「本日」ではないが、昨 日聞いたもので、異常に興奮してしまったもの。それは、クレンペラーの『さまよえるオランダ人』全曲(EMI)。これ、本当に80歳に手が届く老人の創り 出す音楽、芸術ですかね?最初の序曲から気合はいりまくりで、なんというか圧倒的な怒涛の音の塊が聞き手を襲う。これほどまでに、内的燃焼度の高いものは 昨今聞かれるものではないし、また、オケ及び歌手の引き締めも半端ではない。ところが、逆にそのせいか?オケも歌手も彼らの本来持っている特長を意外にも 最大限に発揮しているのだ。
このようなハイレヴェルの芸術を聴くにつけても、クレンペラーのWagnerの全曲録音がこれと、『ヴァルキューレ』の第一幕及び、第三幕の最終場面し か、残されていないのにはつくづく遺憾である。確かに他のオペラ録音は少ないながらも残されてはいるのだが、他の指揮者のスタジオ及びライブ録音と比較し てなんと、寂しいことか!
正直言ってあそこに残された記録は、「楽しみのため」のものではなく、数少ない芸術魂をもった「完成された完全無欠の芸術」である。
その他は、先のCDで火 がついたフリッチャイのJ.シュトラウス集。こちらはDGによるスタジオ録音でステレオの方。こちらの方はややこじんまりしているのだが、やはりその乾い た感じと切れの良さで本家のヴィーンよりも楽しめる。ブリリアント・クラシックスの最新版であるベートーヴェンの合唱曲集はジュリーニのもので。『ミサ・ ソレムニス』も『ハ長調ミサ曲』もどちらも濃い表情とテンポの遅さで、一種形容しがたい、壮大なミサ曲、というよりも沈痛なレクイエムという方が形容の適 切さを感じる。最初は興に乗れなかったのだが、後半、Sanctusより最後までブルックナーの最後の交響曲や、『パルジファル』における厳格な宗教性を 感じた。
で本日に移り、先ずは昨 日より聞いていたクナッパーツブッシュの1954年の『パルジファル』を第二幕、第三幕を通しで聴く。これは、かなり思いのたけを述べた、きわめてテンポ の遅いもの。だが、勿論、彼のことだから、一種の見通しの良さを感じ、更に、オケの重量感も相俟って曲とともにどっしりとした「堪える」演奏であった。歌 手も優秀。リマスターは優秀なArchipelのそれにしては今回はやや広がり感に欠け、しかも、第二幕の始めの方に機械的なミスがありこれには興醒めし てしまった。残念。
お次は軽め、という風に して、フンパーディンクの『ヘングレ』。ローターの恣意的にテンポを動かし、劇的かつ本当の意味でオペラティックな演奏であった。面白さ、という意味では 抜群である。カップリングはアーベントロートがGOLを振った戦中の録音で、同じくフンパーディンクの珍しい『ムーア狂詩曲』。演奏は流石だが、曲自体そ れほど楽しめるものではなかった。エキゾティックなのは分かったのだが・・・。
購入CD聴きのお次は、 E.クライバー指揮によるベートーヴェンの交響曲。1CD目はACOとの第三番と第五番。本家Deccaでもリマスターのが出たので、それはどうなのかは 知らないが、それでもそれほど良いリマスターではない。更に更に、第五の冒頭を聞いて吃驚。擬似ステレオ化するためにピッチが違うでないの!かなり聴いて いて気持ちが悪い。演奏が良いだけに非常に残念。何かアルコールも入っていないのに酔いそう。これは明らかにミスである。日本版でモノーラルだが普通のも のを持っていた故に少々損をした感じ。怪我の功名、とでもいうべきは、演奏の素晴らしさであった。
son.06.nov. 秋の日差しが眩しい毎日。盛夏ではない が、サングラスが欲しいところ。
昨日たまたまTVをつけたら、なんとモノクロで『フィデリオ』を放送していた。が、これが凄い。実は、11/5に戦後オープニング50周年の記念であっ たヴィーン国立歌劇場のライブの模様であったのだ!イヴェント性たっぷりのこの録音、ベームの絶頂ぶりも功を奏して最後は一期一会の爆演になっておった。
<本日聞いた音楽>
昨日はカイルベルトの骨 の或る『ヴァルキューレ』、トスカニーニ指揮管弦楽のショーピース(のようなもの)、E.クライバー指揮のベートーヴェン交響曲第六番、第七番を聴く。
最 高だったのが、クレンペラー指揮の『魔笛』で、その気宇壮大なものは決して「モーツァルト的」ではないが、ドイツの厳格な哲学書を読んでいるかのような錯 覚を覚えた。この曲の持つメルヒェン的な素質を一気に小難しくしたものだが、私にはあたかも初めてこの曲を聞き、更には「理解」したと思った。尚、地の台 詞をカットし、純粋に音楽だけに集中させ、また音、言葉の持つ重要性を分からしめたのはやはりクレンペラーの偉大なる芸術性であろう。録音もEMIにして はかなりの上出来。
で本日。朝からE.クラ イバー指揮VPOのベートーヴェン第九。昨日スピーカーの位置を移動させたせいか、位相空間に引き込まれたような拡がりを感じさせるもので、楽器の分離が 著しく改善され心地よく聞こえる。何度と無く聴いた第九も、指揮者の明晰だが、怜悧すぎない把握感によってドラマではなく、音楽を聴いた感じで好感を 持った。
オペラシリーズはケンペ 指揮METの『トリスタン』。しょっぱなからイゾルデ役のヴァルナイが飛ばす飛ばす。また、ケンペの指揮もスタジオ録音では考えられないくらいに煽るし、 幕の終結部などは、少々雑な感じがするが、オケを叱咤激励して盛り上げる盛り上げる。で、最後まで聞いたのだが、こりゃ凄いわ。第二幕以降俄然、熱気を帯 びて、煽る煽る。扇情しちゃっています。テンポの変化や、がつんがつんならしまくったり、それでいて歌手を巧くのせちゃっているところなど、まさに妙な り!ケンペのスタジオ録音しか知らなかったら、大損だ。同じくMETでの『タンホイザー』もかなり熱く唸っていたし。録音以外に問題は、当時のMETの習 慣として第二幕及び第三幕で各々20分ものカットがあることか。歌手ではやはりタイトルロールのヴァルナイとスヴァンホルムの丁々発止、いや一騎打ち振り が凄まじい。録音は歌手に合わせていたのであろうか(ラジオ録音からであろう)、ヴァルナイの拡がりがあるが、少々どす黒い声がよく聞こえた。絶品なり。
そ の他にはSuitner指揮の珍しい大管弦楽曲集(ヴォルフ、プフィッツナー、R.シュトラウス)(Berlin Classics)、土俗性よりも純音楽に徹したフリッチャイ指揮BPOの第二回目の『新世界より』他(DG)。
mon.07.nov. 昨日は睡眠不足でなんと9時に就寝。久 々の爆睡で5時に起床。でも、まだ寝足りないか?若いなぁ、自分。これを書いている時点で時計の針は9時を少し廻ったのだが、既にへろへろ状態である。
<本日聞いた音楽>
フリッチャイは引き続 く。EMIシリーズで中途半端に終わってしまった、「20世紀の偉大なる指揮者たち」シリーズで(なんと、私はこれとブッシュしか持っていない!)全て未 公開ライブのもの。一つを除きベルリンライブで、リマスターもなかなかである。残念ながらモノーラルが殆どだが、彼の芸術魂をまざまざと分からしめたも の。特に、2CD目のベートーヴェンのそれ。ベートーヴェンの序曲の中で最も完成度が高いと思われる『レオノーレ第三番』、続く交響曲第三番『英雄』の演 奏をきくにつけて、こういった演奏は真の芸術家なしとげえられない完成度の高い、しかも孤高で聖なる触感もするもの。肌触りは決して人に優しいものではな いが、高みに聳える音楽神が聴衆を導いているようなものだ。
mit.09.nov. 気温の急激な低下は少し緩やかになった ようなのか、体が慣れたせいなのか、それほど痛いような寒さは感じなくなった。ただ、寒さ故か、直ちに空腹なるのはどうにもこうにも経済的ではない。
内輪ねたで申し訳ないが、本日地下鉄のニュースTVをみていたら、以下のような宣伝文句があった。曰く、「Der Deutschlands beste Arbeitsvernichter」(多分)。この日、ドイツテレコムの総会で社長が今後数年で大規模なリストラを行うと発表した後に、労組の Verdiが命名したのがこれ。「ドイツ最大の職場切捨て者」とでも訳すのか?正直受けた。
<本日聞いた音楽>
フリッチャイさんはお休 みで、カイルベルト親方のご登場。昨日は、ヴァーグナーやらブラームスやらシューベルトやらが入ったドイツものの他に、スラブものであるドヴォルジャーク の『新世界』他、スメタナの『モルダウ』他を聴く。俄然素晴らしかったのは意外や意外スラブもの。これがまぁ、徹底的に、頑固一徹にドイツドイツしてい て、曲の奥に潜む民族性とか、風景やら心情やら文学性やらを描くような音画的のまさに正反対。みみたこであったはずのスラブものであり、土俗いや通俗名曲 のはずが、高貴で「余りに芸術的な」曲に一変してしまったのが見事。『モルダウ』が特に際立っており、うなる弦、こってりとした遅めのテンポ、沈みそうに なるような重量感いや重厚感といったほうが良いか。目から鱗状態だった。
で、本日はカイルベルト で、先に心の灯火に火がついた『魔笛』。第一回目の録音で、シュトゥットガルト帝国放送管による戦前の録音。あいも変わらずLineの非正規版だが、それ ほど悪い録音ではないどころか、ホワイトノイズを除いてオケ、歌手とともになかなかよく聞こえる。1937年の恐らくラジオ放送であることを考慮に入れれ ば、優れたものであろう。更には演奏も後期の「親方」、「大将」を思わせるようなカイルベルトの「ドイツ性」も良く出ている。
また、カイルベルト。今 度はブラームスの第二番、第四番。これについてはかのKechikechiの盟友Hayashiさんが書 かれていて、それを参考にすると良いのだが、私もBPOの第二番が特に優れた出来だと思う。頑固でこれぞ、ブラームスの響き、解釈だ!というひともいるだ ろうし、私もそう思う。しかーし!お次の第四番が名演であるのは余り注目されておらぬ。オケはハンブルク国立管で、オケの技量や録音だけを取るとやはり 「どんくさい」、「もそっとしている」のは事実ながら、こちらのほうが指揮者の意図をよく酌んで、共に「音楽をしている」という気がするのである。言う所 の「ヘタウマ」というのかな?こっちの方が琴線に響きましたね。
don.10.nov. 寒い時には誰でも鬱になるようだが、私 は今は鬱状態から復帰し、長いこと躁状態。なるったけ、この 状態が続くことを祈るのだが・・・。それでも、やや情緒不安定か?
今、地下鉄の中で読んでいる本は、M.Andersonによる"Klemperer on Music"というもの。ヴィーンで購入した英語版のものである。(あぁ、旧き良きオーストリアシリング時代)その中に出てきたクレンペラーらしいドライ なユーモアを紹介すると。ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世が好んで使った、気に入らない時にいったという、Die ganze Richtung passt mir nichtをアレンジして、Mit anderen Worten - die ganze Richtung passt mir.だそうな。いかにもクレンペラーである。
<本日聞いた音楽>
よっしゃよっしゃ、と 言ったかは知らないが、親方カイルベルトシリーズ。本日一つ目は最初の『オベロン』録音で、ベルリン帝国放送管とのもの。当時彼の故郷であるカールスルー エのGMDであったカイルベルト親方は、同オケの録音は無く、ベルリンやシュトゥットガルトに出張して結構録音している。残念ながら録音は完全版ではな く、第三幕はあれれ、という感じで終わってしまうし、曲自体の魅力が殆ど無い。序曲だけで良いのに、カイルベルトは戦後にWDRケルンと同じく放送録音を している。正直言って全曲録音する必要はそれほど無いであろう。労多くしてなんとかである。
お次は、ステレオ録音の ベートーヴェンシリーズで、ハンブルク国立管との第五、バンベルク響との第六である。まさに正攻法で、奇を衒わない演奏・解釈。しばしば言われるように何 も足さない、何も引かない、でも実は真剣み溢れるものである。いまどきこういった演奏が出来る芸術家がどれだけいるのであろうか?
続きましては、ブラーム スの第一番と第三番。残念ながら一番の方は高音がきんきんして聞きづらいモノーラル録音。「ブラームスの第一番」、「ベートーヴェンの第十番」ということ なく、或る意味淡々と駒を進めるあたりは逆に流石、と唸ってしまう。なるほど、「標準の」ドイツ的な解釈というのはこういうものなのかと、感心と共に納得 してしまった。録音は、リマスターされていないようで、日本版であるこのCDにはわざわざ「マスターテープ経年変化の為、一部お聴き苦しいところがありま す。ご了承下さい。」とご丁寧にも書いてある。どうやら、ドイツの本家からマスターを持ってきて、そのままCD化したようだ。
第三番はバンベルク響とのもので、やはりBPOと比較すると遜色を感じるがそれでも、上記の通り、自分のオケとして意思疎通が優れているといえよう。感 情的になったり、扇情的になったりすることなく、曲想をがっちり抑えるのはやはり親方カイルベルトだからであろう。ステレオという利点を考えても、少々ヒ スっぽい。
残念ながら海外のTeldecはカイルベルトを大事にしておらず、体系的にCDが出ていない上に、リマスターもされてもいない状況である。しかも、DG にいくつか録音があるにも関わらず、これも『アラベラ』意外は放りっ放しで、貴重な『影の無い女』、『カルディヤック』も廃盤のまま。Deccaにはバイ ロイトのステレオ!での『オランダ人』があるものの、劣悪なモノーラル版のTeldecのものが出ている他はステレオは入手不可能である。時刻の文化なん だからさぁ、大事にしようよ!「世界に冠たるドイツ文化」と思っていながら実行していないじゃない。
少し芸風を変えて、久々 のHans Rott。女性指揮者のリュックヴァルト指揮マインツ国立歌劇場フィルハーモニー管による交響曲第一番。やはり、この演奏は非常に、いや異常に優れてい る。録音・リマスターによる所も大だがやはり押し出しの強い解釈も凄みがあって良い。
sam.12.nov. クリスマスが近づいてきたので、ドイツ 人は少しは機嫌が良いが、その他は鬱気味の人が多い。笑えよ少しは!
<本日聞いた音楽>
昨日の親方シリーズは、 ベートーヴェンシリーズ。とりわけ、BPOを振ったメインが第七番の一枚が凄い。頑固煎餅だ。ご隠居さんの知恵だ。力瘤が入った入魂の一球だ。BPOの 持っているドイツ気質を存分に出してくれた。腰が落ち着いていて、やはりこういうベートーヴェン、いや楽聖が基準であった、というもの。第一番と第二番の 一枚もやはりこういった傾向。
親方からケンペへ移行し、彼の代表盤である『ローエングリン』(EMI)。これはただでさえ美しい演奏なのだが、ステレオ配置を換えたら、更に明快で、 EMIのぼけ録音も、こういうように聞くとなかなかどうして、「聴ける」のであった。澄み切った不思議なWagnerだが、先ずは第一番の録音であるかも しれない。
本日の親方はベートー ヴェンで第四番と第八番。及び第三番他。これまた凄い(凄い凄いばかりで芸が無いな)。かつてベートーヴェンがドイツ系の指揮者の試金石であった証左がこ れ。それでいて、単純行動に陥らないのはやはりオペラ指揮者だからであろう。喝采なり。
お次はようやく聞き始め た(なにせ、以前の他の盤は聞きにくい録音だったので)フリッチャイ指揮の『ドン・カルロ』(フランス語五幕版を元にドイツ語翻訳版)より第一幕、第二 幕。フリッチャイがベルリンに乗り込んで初のオペラの新演出の模様。粘る指揮と若々しいフィッシャー・ディースカウのポーザがマッチしないが、録音は Line版よりもよく取れている、と思う。歌手をメインに録ったためであろうか、オケとのバランスがそれほど良いとはいえないし、元テープ自身がそれほど 良いものではないはず。実際のライブ故か、リフレインなどでばしばしカットがあって、あれあれー、状態である。
さ、どんどんいきます。 久しぶりのチャイコフスキー。久しぶりのザンデルリンク。彼は他のドイツ系の指揮者と違って、流石にロシア物をしばしばとりあげる。しかし、これは所謂お 国ものとは全く異なり、徹底してドイツ風味に味付けしたもの。そういう意味ではやはりドイツ人、だからであろうか?得意にしている、又は録音をよくしてい る、即ち優れている、とは限らないのだ。勿論、ここでは優れているどころか非常に優れている。録音も流石に天下の日本のDenonのPCMデジタル録音だ けあって(デジタルデジタルしてはいるが)鮮明に録れている。不思議なことに普段はもっさりしている、ザンデルリンク及びベルリン響も、天下のDenon 録音にかかると、それほどもさもさ、こってりしていない。普段より見通しの良い演奏になったのだが、実際これが彼らの本当のあるべき姿なのかどうかは分か らない。でも、こういう演奏を聴いたのであれば、チャイコフスキー嫌いの私にも、感銘を受けること請け合いであろう。カップリングはアツモン指揮都響によ る『カプリッィオ・イタリア』。
食後のデザートには、ア シュケナージ指揮クリーヴランド管による『アルプス交響曲』。デザートとしては重いが、やはり素晴らしい出来。押し付けることなく、押し付けがましいこと なく(もっとも、ただでさえ押し付けがましい曲だが・・・)巧い具合に味付けしているのは流石である。指揮者アシュケナージはそれほど高く評価されていな いようだが、ことRSに関しては私は彼の解釈に太鼓判を押す。
次はたまたま安かったか ら買った、モーツァルト時代のオーストリアの作曲家、Johann Georg Lickl(1769-1843)なる人によるレクイエムとミサ・ソレムニス。ハンガリーの地方都市で、Licklと関連のある都市Pecsのオケによる もの。残響が過多の教会での録音のせいか、かなりぼやけて聞こえる上に、オケ自体もそれほど巧くない。ライナーノーツによると彼の作品はモーツァルトから 大いに影響を受けたそうだが、Mozartの天才性と比較すると少々かわいそうながら、教会音楽としてはそれなりに良くかけていると思う。ケルビーニから も影響をうけたそうだが、よっぽどそちらの方が部が合う。
mit.16.nov. 寒いですな。予報では、週末にかけて、 日中最高5度にも行かないとか。ほんと、南イタリア移住考えるよ。
<本日聞いた音楽>
ま、なんだな、寒い時に はやっぱり自省的なバッハを。彼の「10大」(自分の中で)作品の一つだと思っている『ロ短調ミサ』を。残念ながら手許には古楽器のものしか殆どなくて、 現代楽器のはヨッフムの二度目の録音しかない。日本にはこの曲を始めて聞いた、壮絶なクレンペラーのものがあった。で、取り出したのは一番聞き応えが或る と思われる、コープマン指揮のもの。なにせ、その清楚さ、というか誠実さに最初にうたれる。曲そのものを虚飾で覆うことなく、ありのままに(当時のまま、 という意味ではない)、等身大で再構造しているのみならず、一種の愉悦さ、というか朗らかさを忠実に具現している、とでも言えようか?オランダのオケは、 ドイツの典型的な厳格さとは程遠い、一種の中庸的で、かつ自主的で見事なアンサンブルを形成している。過激さや、冗長さとも程遠く、末永く聴くバッハはこ ういうのが一番しっくり来ると思う。歌手陣も合唱も録音も秀逸すぎるほど秀逸。
コープマンのバッハはAmazon.deで検索すると190CDほど出ているようだが、『クリスマス・オラトリオ』、偽作『マルコ受難曲』と現在進行中 のカンタータ全集以外は『マタイ受難曲』及び『ヨハネ受難曲』が含まれているBoxで以前に購入したがどれも期待に違わぬ高レヴェルな出来である。
お次は、ラストスパート に入った親方カイルベルトによるブルックナーシリーズ。インターナショナルなマーケッティングでは彼はブルックナーを二つしか残していない。BPOを振っ た珍しい六番とハンブルクでの九番である。名曲だが日陰のような六番をしかもBPOを使ったのは正直言って裏街道まっしぐらであるが、これはやはりセール スを考えてのことであろう。当時ブルックナーのこの曲をまともに録音したのはやはりヨッフムくらいで、クレンペラーとてもほんの僅かな機会にしか取り上げ なかった。全集の一環としてぐらいしか、取り上げられる機会の無いこの「幽玄」的名曲はやはり、売れ筋ではないからといって、クレンペラーの録音計画に反 対したのはEMIのレッグだが、或る意味ではどちらも正論であろう。しかし、やはりクレンペラーの慧眼は流石といえるべきであろうか。我等が親方カイルベ ルトも、この曲を誠心誠意、正々堂々、真正面から見据えて、機能的なカラヤンBPOから流れよりも、無骨さを呼び起こさせた稀有なものであると信ずる。恐 らくBPOも録音としては初めての第六ではないのか?
個人的にはこの曲には思い入れがあって、最初に聞いたレーグナー・ベルリン放送響のでそのとびきり内向的な美しさにひかれ、ヨッフム指揮バイエルン放送 響のでその曲のもつ大自然さの描写にこれまたうたれ、ヴァント指揮ケルン放送響のそれで、意外な無骨さに開眼し、チェリビダッケのそれでは、際限無い・途 方も無く広大な宇宙を感じたのである。ベスト、なぞというものは言わないが、どれも之も名演であるに相違ない。残念ながらクレンペラーのそれは聴いたこと がないし、購入するチャンスをもっていたのだったが、緊縮財政の為に、諦めてしまった。
don.17.nov. 終に、夜の気温が零度付近まで下がって しまった。一部のドイツ人はクリスマスが近いせいからか、機嫌が良い、ように見える。
全く関係ないのだが、最近またもアメリカのSitcomというコメディー番組にはまっている。The King of Queensというもので、残念ながら数年前のものなのだが、すこぶる面白い。毎日7:15から約一時間、二話を放送している。時間的に厳しい時間帯なの だが、これは最近毎日欠かさず見る様に心がけている。デブの旦那と、タイプのラテン系の奥さん、彼女の親父が一つの家で繰り広げられる家庭内コメディーな のだが、そのボケ振り、というか、突拍子も無い展開や、発言がいかす。
<本日聞いた音楽>
昨日からのコープマンの バッハシリーズ。苦手でいまいちぴんとこない『ヨハネ受難曲』。普通のオペラやオラトリオと同様、いくつかのアリアや合唱曲には瞠目するのだが、全体とし ては、やはり不朽の名作『マタイ受難曲』や『ロ短調ミサ』と比較して随分落ちるし、そのため割を食っていると思う。また、テクスト自体もマタイ福音書と比 較しても、遜色を感じる。このコープマンの演奏は勿論のこと、上記のh-moll Messe同様素晴らしい出来なのだし、曲の持つ魅力を十二分に出してはいるのだが、やはりまだまだ私には苦手方面の曲である。ごめんなさい。
古楽器による演奏に火が ついて、クイケン指揮によるハイドンのパリ交響曲集を取り出す。実はこのシリーズ、個人的にはネーミングがついていない曲の方が構成が優れていると思うの だが、なかなかマーケティング的には宜しくないようだし、パリ交響曲集の一環としてではないと売れないのか?かつて大好きだった、82番『熊』ハ長調は、 この曲を聴くごとにかつてアーノンクールがベルリンの音大オケでプローベをしたことを思い出す。それは本当に面白くかつ学術的なもので、アーノンクールの 偉大さを改めて窺い知れたものだった。彼は恐らく、個人的な推測ながら、モーツァルトよりもハイドンの方がよっぽどフィットしていると思うし、ハイドン先 生の曲の方でも、柔軟性というかバッハとは違う許容性があると思う。
話は戻るが、クイケンのもなかなかの出来で、ドライだが、他の連中の馬車馬のとは異なり或る意味暴力性の無い、しかしながら、緊張感のある出来である。
sam.19.nov. 寒い。出不精になる。でも、未だ躁状 態。いとうれしかな。
なぬ、おっと、雪が降り始めた。
昨日、ようやく以前から読破したかった以下の本を読破。何時もは地下鉄の中で読んでいるのだが、其の面白さ、文体の美しさ、そして、内容の意味深さに相 変わらず感銘を受ける。ここでは、言葉の持つ重み、日本国語とはなにか?ひいては日本文化、日本民族、日本精神とか何か?まで、示唆しており、自然そうい うものを考えさせられる。中身は非常に深く、決してアカデミックに陥ることないし、長年の文壇のマイスターとして君臨した谷崎の行間に彼独自の「色気」を 匂わせてくれる、かつ豊富な経験に裏付けられた言葉の美をわれ等に教えてくれる。興味深いのが、同氏の名著『陰影礼賛』と同時期に書かれたもので、一種の 「日本回帰」を明示しているのが、顕著であった。この、「文章読本」は一連の作家によるものの嚆矢となったもので、他には、三島、川端、丸谷才一、井上ひ さし等が書いているが、ある批評では、この名称を名乗って良い唯一の本だとか。全く持って傾聴ならぬ「傾読」に値する本だ。
*谷崎潤一郎著 『文章読本』 中公文庫
<本日聞いた音楽>
昨日篇
ベルリン古楽アカデミー バッハ:ブランデンブルク協奏曲全集。月並みながら古楽器によるロックのような、フレッシュで、劇的なバッハ。とてもシャープで、快刀乱麻を断つかのよ うな清々しさを感じた。それにしても、こういう演奏で聴くと、バッハは全く持って古くない。
同 じく、古楽器によるもので、お次はハイドン。パリ交響曲の後半。パリ交響曲になってぐっと世界が変わったシンフォニーの一群で、以前までの彼の交響曲と比 較して、その熟成振りが良く分かる。
久 々にRS。最近、ほんとご無沙汰だったのだが、この時期にぴったりの『四つの最後の歌』を聴いたのが契機となって、RS開始。先ずは名盤の誉れ高いセル指 揮シュヴァルツコップ歌唱によるEMIのもの。歌手、オケ、解釈とも完璧で、昂然と光を放つ高貴なものだが、どうもこういう完全無欠な演奏を聴くと、日本 人である私にはもう一つの余裕というか、余白が欲しくなる、という感情が自然出る。芸術としては立派で、完成度は最高度ながら、一種の遊び、というか余韻 を聴衆に味合わせてくれるものが結局は好きなのだ。そういう意味で、日本人には完璧を嫌う、というか腹八分目という感覚、なるものが真の芸術、だと思う。 ま、これは所詮趣味の問題なのだし、この曇りの無い、非の打ち所の無いものも楽しめるのも確かなのだが・・・。
お 次もRS。珍しい合唱曲集。Hayko Siemensという合唱指揮者がミュンヒェン響を振ったもので、RS週間におけるライブの模様である。が、これは問題だ。先ずは、オケが下手過ぎる。ラ イブという状況下を考慮したとしても、この精度の低いオケ、合唱はCDという媒体の存在意義を感じない。また、録音もいい加減だ。こもりがちで、分離の悪 さはいかなるAudioで聞いてもこうなるはず。もっと問題なのは、こういった珍品、というと言い過ぎかもしれないが、演奏史上で余りプログラムに乗らな いものを販売するのは実に結構だし、リスナーにとってはこの上なく嬉しいのだが、やはりクオリティーが付いてこないと、個としての価値が減ずるのは当然で あろう。こういった、投槍の販売姿勢、は早々改めるべきだ。哲学無しして、人はついてこない。
その他、タックウェルとケルテシュによるホルン協奏曲集。
で、本日篇
購入したものの、忍耐が 必要な曲で、やや苦手としている曲を週末故にようやく取り出す。尤も、第一幕と第二幕のみだが。ヨッフム指揮バイエルン国立歌劇場による実況、『マイス タージンガー』である。原盤はOrfeoの正規版だと思うが、音が痩せている上に、演奏も記念のものなのだが、それほど面白くは無い。
鍋Partyの前、後に 結局全曲聞いてしまったもの。それは、ケンペ指揮ミュンヒェン・フィルのブルックナー交響曲第四番。
mit.23.nov. 寒さも少しは慣れた、というか和らいだ 感あり。日本は勤労感謝の日だったようですね。「寒さに負けず・・・」っと。
<本日聞いた音楽>
ベルグルンド指揮ヨー ロッパ室内管 シベリウス:交響曲全集 Finlandia 4CD
こういった寒い時にはやはり、寒い曲を。私の場合には獨墺から右に行かないで左へいくタイプ。即ち、シベリウスに代表される北欧へと足ならぬ、耳を向ける のであった。北欧の冬ほど「色の無い」冬では、ドイツは決してないが、メンタリティーの上で、やはりシベリウスは聞かざるを得ないのである。ベルグルンド の全集のうち、一番最近のもので、厳しさの中に、若さというか爽快さを感じさせられるものである。驚くべきが、以前のヘルシンキ・フィルとの全集よりも明 るく、よりフリッシュさを感じさせるのはただ単にオケが「若い衆」だからではあるまい。本当に信じられないのだが、以前の二つのものよりも、総じて外的で あるということだ。勿論悪い意味ではなく、傾向として内的な演奏になりやすい(本当に良い演奏だけだが)ものを、ここまでそして、一種の「老獪さ」が無い 状態で、テンポも年齢と共に遅くなるのではなくて、こういった解釈が産まれたということ自体に、指揮者のメンタルな若さに感嘆せざるを得ない。
fre.25.nov. 待望の週末である。週末は誰にでも来る 密やかな幸せである。
本朝、というか要は起床後外を見ると、なんと積雪。道理で寒い訳である。ただ、降雪の時の寒さと、単なる寒さとでは心なしか何かが違う。それは、嬉しさ 交じりの寒さ、といったところか?
地下鉄用の本はその内容の面白さ故に、帰宅後も引き続き鞄から取り出し結局読破してしまう。ヴィーン好きには堪らない内容だが、やはり専門家故か哲学の 方にやや力点を置いている。ヴィーンを概要的に把握するには小難しい評論よりも、こういったエッセイが一番良いかもしれない。
*森本哲郎著 『ウィーン 世界の都市の物語』 文春文庫
<本日聞いた音楽>
昨日は、帰宅後速攻で、 『トリスタン』を聞き始める。1953年のバイロイト実況で、この年初めてバイロイトに出演した御存知ヨッフムの『トリスタン』である。おなじみのこの指 揮者特有の煽りが、オペラで、ヴァーグナーで、『トリスタン』にまさにビンゴで、愛欲の泉にどっぷりと浸けられてしまった。録音も流石バイロイトだけあっ て優秀。歌手も、当時の一流かつ名目共にWagner歌手を揃えており、その妙技を楽しんだ。残念ながら第一幕は1CDに収まらずに、第二CD目冒頭に 渡ってしまったのだが、そんなことは些細なもので、Jochumの扇情的、いや欲情的?とでもいうべき熱い血潮を感じた。Wagnerまさに、こうあるべ し!
お次は、冒頭部が気に なっていた、『未完成』。せっかくなら最高の演奏で、ということで取り出したのが、凍れるような表現だが、その奥深くに潜む灼熱の情熱を持つクレンペラー のVPOによるライブ録音。これは、高校時代にたまたま手に入れた限定版のもので、VPO設立150年のアニヴァーサリーCD。最近Testamentか ら体系的に出たが、当時は正規版としてはこれが唯一のVPOのライブであった。演奏は言わずもがな。宇宙の壮大さと、なんともいえない叙情身がたまらな い。カップリングは『運命』で、これも驚異的な演奏である。
深夜にはやはり瞑想的な 曲を。カイルベルト指揮ハンブルク国立管のブルックナーの第九を。オケの荒々しさと録音の稚拙さを考慮にいれなくとも、これは名演であろう。正直指揮者の キャラクターと曲想がマッチしているとは思えないのだが、意外や意外これが大ヒット。
さて本日は、
やはり、昨日から火がつ いた『トリスタン』。ヘーガー指揮ベルリンのオペラ座で戦中のもの。これも、「爆演」の名に恥じない、煽りまくっている演奏。第一幕のみ。
お次は昨日第一部を聞い たコープマン指揮による『マタイ受難曲』。TVを見ながら聴いたのでそれほど集中できなかったのだが、真摯さとデリケート、柔らかさが同居する最高のスタ ンダードな演奏であるはず。歌手も、合唱も録音も優秀すぎるほど優秀。
ブルックナー第九番は海 賊盤のヨッフム指揮ミュンヒェン・フィルへ(METEOR)。この曲の最高の演奏の一つと思っているもので、文字通り瞑想的、かつ宗教的雰囲気を極限まで 推し進めたもの。そして、絶妙なまでのオケの呼吸。こういうものならばんばん海賊盤で出して欲しい。海賊盤の海賊盤たる所以はここにあるはずであるから。
son.27.nov. 昨日は最近知り合いになった日本人夫婦 と一緒に韓国料理で寒さ対策の暖をとる。その後、バー兼レストランでビールを飲んだあと、小生の部屋に招待。久しぶりの、しかも日本語による音楽談義で時 が経つのが忘れる。
*T.シュトルム著関泰祐訳 『みずうみ』他四編 岩波文庫赤
全て珠玉の小品集で、数時間あれば読破出来るが、小説の場合は内容及びイメージを しながら読み進めるので、かみ締めるように評論より時間をかけてじっくり読む。
中身は・・・
みずうみ Immensee、
マルテと彼女の時計 Marte und ihre Uhr
広間にて Im Saal
林檎の熟するとき Wenn die Äpfel reif sind
遅咲きの薔薇 Späte Rosen
どれも、シュトルムの初期の作品で、初期の作品独特の叙情性が北ドイツ風味から味わえる。ブラームスを聞きながらこれを聴いたので、耳も目も心もそこには 北ドイツ!心のなかにぽっと、暖かい松明の火がついた感じ。『遅咲きの薔薇』では今はまっているトリスタンの内容が出てくるので、更によきかな。訳は昭和 27年に再度なされたものなので、文体がやや違和感を感じるが、シュトルムの風味は損なわれていない。内容はとりわけ、『マルテと・・・』が一番気に入っ た。新潮文庫には高橋義孝訳、全集もの、その他の訳があるようだ。
最近見つけた素晴らしい音楽のリンク。
オッフェンバックの紹介、及び録音、 コメント。
Frida Leider。世紀の大歌手。ベルリンに関 連ある戦前・戦中の歌手で、そのアンソロジーがNaxosHistoricalからも出ているのを購入して、気に入ったもの。
Eugen Jochumの Discography。かなり前から休業中だったが、最近ようやく復活した。データなどは未だ以前のもののまま。
小生のDisはホルライザーとエルメンドルフを少し更新。
<本日聞いた音楽>
これまた昨日のだが、 HegerのTristanを一気に、第二幕と第三幕を聴く。戦中というよりも、戦中末の時代を反映しているかのような(実際録音されたのは、1943年 5月だから、未だドイツが威勢良かったころだが)、阿鼻叫喚的な演奏で、この曲のまずあるべきプロトタイプであろう。歌手も当時のWagner歌手の万全 な布陣。
ケンペ指揮ミュンヒェ ン・フィル ブラームス:交響曲第一番、第三番 独ARTS
時代は戦後、しかも、奇跡の復興を遂げた西ドイツの録音で、ケンペ晩年の録音。オリジナルが悪いせいか、オケもリマスターされた録音もそれほど良いとは思 えなかった。
で本日日曜日も、アイル ランド恍惚、愛欲劇場四時間ヴァーグナー編、であるまたまたTristanへ。恐らく全曲として最初のスタジオ(放送録音?)であろう、Hans Weisbach指揮ライプツィヒ放送響によるもの。流石当時の演奏、というか、楽器や歌いまわしにポルタメントが施され、録音も所々聞きにくい箇所があ るが、1938年ということを考えれば一種驚異的な鮮明さかもしれない。ただ、演奏は良くも悪くも普通の演奏で、Tristanということを考えれば面白 みに欠けるかもしれない。尚、CDは悪魔のドイツレーベルCantus/Lineで、2CD、2セット。しかも、収録時間お構いなしに幕毎にぶつぶつ切れ ている。このレーベル、他のヒストリカルレーベルのものを更に自社から出すという、屋上屋を架す全く、というか殆ど無意味なレーベルなのだが、この録音は 今ではCDとしては他から出ていないので、貴重かもしれない。印刷や、解説もちゃちいこと極まりないし、驚くべきことはたまに裏が青い・・・。このような やくざな商売、他にもHistoryレーベルとか、その系列は安いとはいえ、販売哲学に全く感心しない。
尚、指揮者のHans Weisbach(1885-1961)はシューリヒトの後のライプツィヒ放送響の主席指揮者(1933-39)だったようだ。(詳細は小生の知られざる 指揮者で!)。録音はこの『トリスタン』全曲、『Rienzi』抜粋、『ファルスタッフ』(ドイツ語全曲)、ヴィーン響を振った、『トリスタン』第二幕、 『マタイ受難曲』がある。ケンプの伴奏のもあるようだ。
今日はどうやら Wagnerさんが御呼びのようで、お次もWagner。Carltonから出ていた交響曲ハ長調(Heribert Beissel指揮ハンブルク響)、『恋愛禁制』序曲(Alois Springer指揮ルクセンブルク放送管)、『妖精』序曲(Alois Springer指揮ハンブルク響)、『トリスタンとイゾルデ』前奏曲と愛の死(管弦楽ヴァージョン)(スクロヴァチェフスキー指揮ミネソタ管)。ミネソ タ管以外は殆どVoxでしか聴けないし、レヴェルが低すぎる。音も酷い限りで、珍しい曲でなければ決して買わないであろう。
二夜に渡る「ベルリン封 鎖」に関する映画の第一夜を見た後、またしてもWagner。彼の初期の作品、しかも合唱曲である『使徒の愛讃』とブルックナーの最後の方に属する合唱曲 である『ヘルゴラント』。指揮は際物の曲が好きなWyn Morris指揮、これまた無名なオケSymphonic of London。レーベルはいまいち良く分からないIMPというもの。ジャケットには録音年も書いていないし、録音自体もAADだが、オケも録音もなかなか 頑張っている。Wagnerのほうは、Dresdenで書かれたもので、33分にまたがる大規模な管弦楽を伴う大曲。しかし、オケは最後の方で:24分あ たりからちょろちょろ出てくる。曲想は『オランダ人』、『タンホイザー』の巡礼の合唱、及び後期の『パルジファル』での聖杯の合唱のようなもの。録音は ブーレーズ、プラッソン他しかない。ブルックナーの方はこの曲バレンボイムが二度の全集で、二度録音している以外には今では見つからない。曲想は詩篇 150や、Te deumを連想する、壮大でカトリック的な大伽藍の曲である。管楽器の壮麗さが心地よい。
mit.30.nov. 本日は何もしない一日。どうも嫌だな、 こういうの。なんとなく、頭も冴えないし、やる気も食欲も無い。困ったものだ。行動しなければならぬのに。
あぁ、既に11月も終わりですね。「明治も遠くなりにけり・・・」ではないが。
本日読んだ本は、
*岩井忠熊著『西園寺公望 -最後の元老-』 岩波新書
昨年の12月に読破したもので、再度読了。再度検証したことだが、やはりこの作者の切り口は優れている。単に、歴史の叙述及び西園寺の伝記ではなく、現在 から歴史全体及び其の中の西園寺を考証し、そこに潜む問題点及び批判を展開しているのは、歴史認識として当然のことなのだが、それほど有名ではない人に対 してこういったことを行うのがいかに難しいことか。西園寺がなぜ失敗したのか?歴史の中で極度の存在感が無かったのかを、叙述するスタイルは秀逸であろ う。
<本日聞いた音楽>
シュミット・イッセル シュテット指揮NDR響 ヴェルディ:『アイーダ』(ドイツ語版全曲) 独Walhall。
最近火がついたVerdiいやAida熱にうなされ、本日も手に取ったもの。当時の豪華な歌手陣と地に足ついた、しかし適度な「荒れ具合」もある指揮 者。オケも録音も優秀である。歌手ではやはりラダメスのロスヴェンゲが耳目を惹いた。声と表現共にエクセレント!
ボールト指揮LPO、 LSO ブラームス:交響曲第一番他 蘭Disky
御存知ロマン指揮者のボールトによるブラームス。まさに適材適所といったところで、ボールトの芸術性の高さを如実に示したものの一つであろう。ブラーム スはロマンティックであらねばらなぬ、というその程をイギリスのオケから引き出したもので、しばしば評価される、「イギリス紳士的穏健」な演奏とは一線を 画している。この芸術家ももっと再評価されるべきであろう。この人に限らず、大体においてイギリスの指揮者はそれほどよく評定されていないのが現実であろ う。イギリス人の指揮者の査定となると、温和で中庸で、イギリスの音楽の専門家、というそれ以上でもそれ以下でもない曖昧で不明瞭なものだが、それは飽く までも偏見であり、視野を狭くしているようなものだ。
イギリスの指揮者で優秀、というか高いランクにあるのは、ビーチャム、バルビローリ、ボールトが筆頭であろう。勿論、ドイツ系指揮者のようには多く録音 を持っていないのは事実ながら、彼らの演奏はいつでも、注目に値するものばかりであった。
などなど。
▲ [Top]


![Beethoven:Symphonies 3/5/6/7/9 [UK-Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NYSBVACNL._AA240_.jpg)