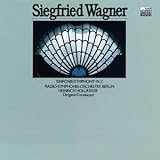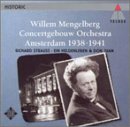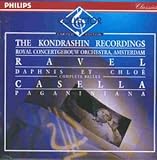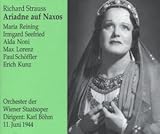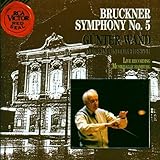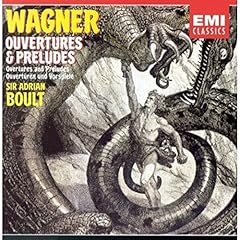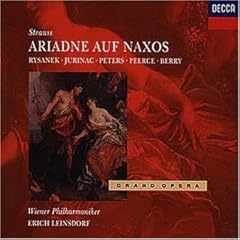"Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen..."
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; ���L]
�u�����āA�����������z�͏���ł��傤�E�E�E�v�Ƃ����̋Ȃ̈�߂��� �Ƃ������̍��͏��������������A�����l�� �Ă��邩���L���ꏊ�ł��B
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; ���L]
�u�����āA�����������z�͏���ł��傤�E�E�E�v�Ƃ����̋Ȃ̈�߂��� �Ƃ������̍��͏��������������A�����l�� �Ă��邩���L���ꏊ�ł��B
|
[A.D. 2006 / Heisei 18 / Kôki 2666] October; Oktober; Ottobre; Octobre [Last modification: 30.Oct.2006] |
son.01.oct. �@�\���ł���B�����f�U�C���E�X�^�C���E�t�H���g��ς��āA�u�H�炵���v�B���₷�� �Ȃ����ł��낤���H���ꂪ��ԑ厖�Ȃ��ƁB
�@�T����TV�f��́A�w�I�[ �V�����Y�E�C���u���x������B�X�g�[���[�͑債�����Ƃ͂Ȃ��̂����A�W�J���ʂ̃_���f�B�[���A�N���[�j�[�A�ƃu���b�g�E�s�b�g�A�K���V�A�̖��� �Ȃ��Ȃ��ł������B��]�ł͖��҂��g�����Ȃ������Ă��Ȃ��A�Ƃ����̂����������A�܂��A���������̂͊y����ł݂���̂�����ˁB
���̌�X�ɐ[��ɁA�w�L���E�r��Vol.1�x�����邪�A�q�b�g�̊��ɂ͂����������Ƃ��Ȃ��Ɗ������B�Ō�̏�ʂȂA�r�c���Ƌg�Ǔ@�𑫂� ���悤�Ȃ��̂��������A�܂��A���{�ꂪ���������͓̂��R�̂��ƂƂ��āA�X�g�[���[�⊴�o���ꎩ�̂��A���e���Ƃ����Ă悢�B
���{���� �������y��
�@�g �X�J�j�[�j�w��NBC���@�o�b�n�A�n�C�h���A�`���C�R�t�X�L�[�@��Naxos
[�ʐ^����]
�i�o�b�n�A�n�C�h���́A�o���b�N�̗�O���̂悤�Ȃ��̂�\���������̂��H�`���C�R�t�X�L�[�́w�ߜƁx�͋���i�����A������h���C�ʼn��y�̔w��ɂ��镶�w ���Ȃǔ��o���\�o���Ă��Ȃ��B�������Ȃ����A����قNJ����͎Ȃ������B�ŋ߃g�X�J�j�[�j�͂����Ƃ��Ă���B�j
�@�g �X�J�j�[�j�w��NBC���@�O���b�N�A�u���[���X�A���X�g���@��Naxos
[�ʐ^����]
�i���܂��͐F�X�ƁB�{�����̓u���[���X�̑�O�ԁB�Ȃ����v���̐^�ɋ��܂��Ă���B���ς�炸�h���C�ȉ��t�����A�u���[���X�͒��X�Ɂ[�g�X�J�j�[�j�� ���Ắ[���}���e�B�b�N�Łu�u���[���X�v���Ă���B�t�B���n�[���j�A�ǂƂ̑S�W��Testament�ŏo�Ă��邪�A����͒��X�̉��t�������ȁB��x������ ���������̂��B
�@��͂Ȃ����AS.���@�[�O�i�[�́w���������̚��x�i���������Ȃ�Ă����ł��傤���H�j�Ƃ������́B������R.�V���g���E�X�y�уt���p�[�f�B���N�̃I�y ����ł��������́B���X������}���h���̃e�C�X�g������̂����E�E�E�B��������ċh�������A�x���O�����h�w���{�[���}�X���ɂ��V�x���E�X���S�W�� �����Ō�̍Ō�̎��^��i�A�wEn Saga�x���f���炵�������B
mon.02.oct. �@�����Ȃ��Ă��������B
�@�D���ȉ��y���肾���ł͂Ȃ��A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����y������̂ŁA�����ł͂Ȃ��A�y����ō��܂ŕ����̒��ŕs����CD�Ȃǂ����o���B
�@�e��\�t�g�̃X�L�����APC�̃o�b�N�O���E���h�Ȃǂ�A�g�����Ƃ������Ċy����ł���B
���{���� �������y��
�@�w ���c�F�w��BPO�ALSO�@�w���c�F�F�����ȑ�1-6�ԁ@��DG
[�ʐ^����]
�i�Ȃ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�I���W�i���e�B�[���]�芴�����Ȃ���i�ł���B�Ȃ�ŁA���X�V���t�H�j�[�����̂������ɏ����Ă���̂ł��낤���H������A�ˋC ������̂Ȃ�܂������A���ꂶ��X�g�����B���X�L�[�����u���㕗�v�ɖ��t�����������ł��낤�B�j
�@�o�[ �_�[�w���x�������E���W�I���@���H���t�E�t�F���[���F�I���g���I�wLa Vita Nuova�x�i�V���������j�@��Koch
�i�t���p�[�f�B���N�̃����q�F�����A��o�b�n��^����"����"�@�����y�AR.�V���g���E�X�����肵���f�批�y�̂悤�ȁA�_���e��������������ɂ����Ȃ� ����A�߂�߂�̃��}���e�B�b�N�ȃ}�[���[�́w���l�̌����ȁx�̂悤�ȃI���g���I�ł���B�ɂ߂��͎��������ł��낤�B�����Ȃ�Ȃ����y�ɑ�����g �݁A���y�Ƃ����̌njR�����U��͔������̂́A�I�P�̃R���f�B�V�����A�^�������ڂ��Ă���̂����Ɏc�O�ł���B�j
�@���ɂ�Klee�w���V���^�[�c�J�y���E�x�������ɂ��j�R���C�F�w�E�B���U�[�̗z�C�ȏ��[�����x�i��BerlinClassics�j�ȂǁB�S�����炩�� �Ȃ�t���[�~�q�w���h���X�f���\���ˍ����c�ɂ��16,17���I�̃A�J�y�����e�b�g�W�i�����ԁj�B
die.03.oct. �@�����̂����A�܂������g�[�����Ȃ��A�g���Ȃ��B
�@�����́A�w�h�C�c����̓��x�Ƃ������ƂōՓ��B�܁A�O���l�ɂł��Փ�������͔̂��ɂ��肪�����b�ŁA���ɖ���I�ł���E�E�E��H
�@�܁A�ǂ��ł��������B
���{���� �������y��
�@�J �C���x���g�w���o�C�G���������̌���@R.�V���g���E�X�F�w�T�����x�@��Orfeo
�i�J�C���x���g�ɂ�����ڂ̘^�� �Ń��C�u�BOrfeo�̃o�C�G���������̌���Live�V���[�Y�̑��e�炵���B�����̕����ɐQ�����Ă������u���o�������v�B���̔�������̂������A���̉� �t�ɋ����I�ȑO�͂���قǂ��̐����������Ȃ������A���t�A�Ȃ������̂����A4�N�ȏ�o�߂��A�n�����āH�[���̊ԕ�����ł��鎩�g�����Ȃ�u�ω��v�����Ǝv ���[�O�����Ƃ������y���߂��B
�@�J�C���x���g�̓J�������̔��ɂɈʒu���Ă���Ǝv���B�J�������̂��K���X�z���ɒ��߂�A�C�M���X�Y�̖��e�B�[�J�b�v���Ƃ���ƁA�J�C���x���g�̂���́A �����Ƃ��Ă��Ȃ�����A�G���Ċy���߂銴�G������{�M�̓y��̂悤���B����ɂ��Ă��A�J�C���x���g�̃I�y����グ��A����̖��̓I�y���w���̍��{ �ł���A�ō��̗�ł���B�Ō�̐���オ��ɑ����r�����ł���B
�@�̎�ł͑薼���̃{���N�A���J�i�[���̃z�b�^�[����͂薼�̎�Ԃ�ł���B
�@���A���}�X�^�[�͂��̂���l�B�N���E�X+�A�C�q���K�[�����R���r�� ����E�E�E�B�j
�@�x�[ ���A�������g�A�z�����C�U�[�w��VPO�@R.�V���g���E�X�F�w�l�̍Ō�̉́x�A�I�y�����A���A�W�@��Decca
�i�V���g���E�X�̑����B���V���g���E �X�̂��ł�����Lisa della Casa�ɂ��V���g���E�X�W�听�B���}�X�^�[�����O���������������A�w�l�̍Ō�̉́x�ł͒ʏ�̂��鏇���ł͂Ȃ��A�w�b�Z�ɂ��wBeim Schlafengehen�x�����Ȗڂł���B3-2-1-4�̏��ł���B���͂�⋇���Ȃ����ɂ�����Decca�̘^���ł���BLegends�V���[�Y �̈�ł���A96kHz-24-bit�Ȃ�Ƃ��Ń��}�X�^�[���Ă͂�����̂́E�E�E�B
�@���@�C�I�����E�\���͂�͂�{�X�R�t�X�L�[�ł��낤���HVPO��R.�V���g���E�X�̊ܗL����u�댯�ȁv�^����]�����ƂȂ��`���Ă���B
�@�I�y���A���A�W�ł́A��ȉƂ̉��ł��郂�����g�ɂ��w�A���x���x�A�ŋߖS���Ȃ��Ă��܂����z�����C�U�[�ɂ��A�w�A���x���x�A�w�i�N�\�X���̃A���A�h �l]�A�w�J�v���b�`���x�ł���B
�@�����A�x�[���̎w���Ԃ�����A���t�w���Ȃ���A�I�P�̖��͂ƋȂ̔��킳���\�ɕ\�o���Ă���̂̓������g�ƃz�����C�U�[�̕��ł���B
�@della Casa�̘e���ł߂�̂́A�M���[�f���ƃV�F�b�t���[�ł���A�����̃��B�[���E�i���[�c�@���g�j�E�A���T���u���ł���B���ɃV�F�b�t���[�̃}���h���[�J�� ���Ƃ����̂��邱�ƂƂ�������I
mit.04.oct. �@�g�c�G�a���́w���y�@�W�]�Ɣ�]�T]�i�������Ɂj�ɁA�V�F�[���x���N�̌����� �āA�i�������������o�������邪�j�u�������Ǝv�����Ƃ�������l�ԂłȂ��āA���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������Ă���l�Ԃ��A�|�p�ƂƂ������̂ł���v�A�� �����̂��ڂ��Ă���B
�@���̌����X�ɔ��W���āA�u���������Ǝv���l�Ԃ����ł͂Ȃ��A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����y�������Ă���l�Ԃ��A�^�̉��y���D�ƂƂ������̂ł���v�Ƃ������� �ϑt�������B
�@��X�A�ꉹ�y�t�@���́A�����A�Ƃ����������Ή��y���y����ŁA�����̍D���ȂƂ��ɁA�����̍D���ȉ��y���A�����̍D���ȉ��t�Ƃ̂��ƚn�D���Ă���̂� ���A���ɂ́A���⊸���ĐV�������̂ɒ��킵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������邵�A�������Ȃ��Ǝv�l�̒�~�y�сA�d�����A�]�זE�̑މ��Ɍq����ƐM����B���Ȃ킿�A �������x�[�g�[���F�����A�u���b�N�i�[��烔�@�[�O�i�[���A�}�[���[�������āA���y������Ă͂����Ȃ��B�܂��A�t���g���F���O���[���A���@�� �^�[���A�N�����y���[���A�N�i�b�p�[�c�u�b�V�������������āA�u�ǂ����t�v�Ƃ���̂����l�ɋX�����͖����B�̂ɁA�y���݂̉��y��e�A�Ƃ����ȏ�ɁA�� ���Ė�������̂ł���A�u����̉��y�v�Ƃ������ɁA��ɐV�������������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�܂��A�ȑO�͌����ł��������t�≹�y���A���ɂ��̕]�� �������Ɉʒu����ꍇ�����邵�A�ȑO�Ɠ����悤�ɕς��Ȃ���������Ȃ��B�������Ȃ���A��X����ɐS�ɗ��߂Ă����ׂ����Ƃ́A�u��v�̓����y�сA�s ���̒n�ʂĂ�����̂ɒǐ����邾���ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B
�@����āA�����̏����Ȏg���ł͂��邪�A�����������u����̉��y�v����Ɏ����Ă���A�V���Ȃ鐢�E�ւƃA���J�[��������悤�ɓw�߂Ă���B
���{���� �������y��
�@Wit �w���|�[�����h�������i�J�g���B�b�c�j�@�N���[�Q���i�`�F���j�@�V���X�^�R�[���B�`�F�`�F�����t�ȑ��ԁA���ԁ@��Naxos
�i�V���X�^�R�[���B�`�͋��ȍ�ȉ� �ł���B�˔\�����ȉƂł͂��낤�A�Ǝv���Ă���̂����A�ǂ����Ă������ۂɂ��̐S�����������Ă����Ȃ��B�ܘ_�A�����Ȃ͑������������A���t�Ȃ̓s�A�m�A ���@�C�I�����A�����Ă��̃`�F�����D�ꂽ��i���Ƃ͎v���B���A�ǂ��ɂ������ɂ������̕��@�ɍ��v���Ȃ��̂ł���B������Ƃ����ĕ����̂���߂��肵�Ă͂� ���Ȃ��̂�����A������o���Ă݂��B
�@�`�F���̃N���[�Q���́A����Naxos�Ńh���H���W���[�N�y�уG���K�[�̃`�F�����t�Ȃ�CD�ŋZ�p�y�т��̊��G�͐܂莆���B�����ă`�F���͕�����悤 �Ȋy��ł͂Ȃ��̂����A�D�ꂽ�`�F���t�҂ł��邱�Ƃ͕�����B�܂��A�ӊO�ɂ��I�|����I�|�|�[�����h�̕����I�P���Ȃ��Ȃ��ɂ������肵�����͂������Ă��� �̂ɂ��������ĉ�ł���B
�@�Ȃ���ɂ���Ă̐Q�Â������A���Ȃ��Ƃ��܂�Ȃ��͂Ȃ��Ɗ������B���������Ђ˂�����������܂ɕ������ɂ͗ǂ��B�^�����ŗD�G�Ƃ͂����Ȃ����A�I�P�� ���͂��o���ɂ͏[��������قǗD��Ă��悤�B�j
�@�N�[ �x���b�N�w���o�C�G�����������@�h���H���W���[�N�F���ȏW�A�������W�@��DG
�i�h���H���W���[�N�͂��̃����f�B�[ ���C���̖L���Ȃ��A�ŁA�Ȃ��Ȃ��ɗD��Ă����i�������Ǝv���A�̂����A�����ɘ^�����ꂽ���́A���ɏ��ȈӊO�A�������͂�����\���������Ⴒ���Ⴕ�� �����ɒ�������B���X������̂�����̂����A�S�̂���Ղ��Ă݂�ƁA�ǂ����^�╄�����Ă��܂��B�j
don.05.oct. �@����͈̂����Ȃ��Ƃ��������B���A�{���w������CD�̖ʎq���݂�ƁA��͂� �ȁB�B�B����ł���B
�@�����莺���g�[���悤�₭�������āA�����v�������Ȃ��ōς�ł���B���肪�������Ƃ��B��͂�A�l�ԈߐH�Z�A�ǂ������Ă����߂Ȃ̂ł���B
�������w������CD��
���A�[�m ���N�[���w���A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�ǁ@�n�C�h���F�U�������Z�b�g�W���@��Warner�@5CD�@22.99E
���N���t �g�w��CSO���@�V�F�[���x���N�ҋȏW�@��BMG Sony�@6.99E
��Belder �w��Musica Amphion�@�o�b�n�F�u�����f���u���N���t�ȑS�W�@���u�����A���g�@3.99E
���{���� �������y��
�@�N ���t�g�w���@�V�F�[���x���N�ҋȏW
�i���^�Ȃ̓��e�̓u���[���X�̃s�A�m �l�d�t�ȑ��ԁi�V�F�[���x���N�ҁj�A�o�b�n�F�w���A��]�i�V�F�[���x���N�ҁj�A�o�b�n�F�R���[��2�i�V�F�[���x���N�ҁj�A�V���[�x���g�F�h�C�c���� �i�E�F�[�x�����ҁj�ł���B60�N�㏉���̘^���ł���A�^�����I�P�[�V�J�S���I������قnj������܂���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�N���t�g�̓u���[���X�̂�� ��ɍēx�t�B���n�[���j�A�ǂƘ^�����Ă��邪�A�����MD�Ɏ��^���Ă���B
�@�N���t�g�͈ꐶ�ɃV�F�[���x���N�̍ő�̗i��҂̈�l�ł���A������CD���s������A�{���������肵���B�����A�ǂ������ґ����ǂ����y�ƂƂ͂Ȃ�Ȃ��B ���������ă��C�i�[����i���ォ�H�j��CSO������قǂ܂łɂ����Ȃ͈̂ӊO�ł������B�g�����g���Ƃ́w���A���x�������ɕ��������̂����A����͂��� �Ŋy���߂��B
�@�A�[ �m���N�[���w��ACO�@�n�C�h���F������68�A93�A94��
�i�܂��Ă܂����́A�A�[�m���N�[���� ���n�C�h���B�ނ̃f�t�H�����������߂��ɂ�āA�v�킸�ɂ���Ƃ��Ă��܂����A�n�C�h���̂���̓o�b�n�Ƃ͈Ⴄ���̂́A���߂̘g�����L���A��e�͂� �傫�����̂́A����䂦�ɍ����w���҂ɂ�����ƁA����͒��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��̂����낵���B
�@�������A�A�[�m���N�[���̎�ɂ�����ƁA�܂��ɐ������̂悤�ɁA��ђ��˂�A�т����肳������A��т�^���Ă����A�y���݂��������Ă���� �Ƃ������ŁA�܂��Ƀn�C�h�����Ă���C���������ĂȂ�Ȃ��B
son.08.oct. �@���Â肪�I���Q���Ă�����A�����ɂ��āA�Ȃ����������܂�Ă��閲�܂Ō���n ���B�܊p�^�C�K�[�o�[���h�����̂ɁE�E�E�B
�@�ŋ߂��A�u���m�Ȃ�vCD���悤�ɂ��Ă���B
�@�J�C���x���g�w���V���g�D�b�g�K���g�隠�����ǂɂ�関���S�Ȃ���h�C�c��ł́wTurandot�x�i��Koch�j�͂��A�ʔ��݂Ɍ�����Ȃ�����A�� ��قǂł��E�E�E�B
�@�I�[�}���f�B�w�����t�}�j�m�t�����ȑS�W�͂��������肵�����̋Ȃ����A�Ȃɂ�Sudoku�����Ȃ��炾�������炻��قǏW���o���ĕ������킯�ł͂� �������i��Sony�j�B�}�[�[���̑S�W�ł��~�������ȁH
�@Bass�w���ɂ��R.�V���g���E�X�̈ꖋ�I�y���w���a�L�O���x�i�w�u�a�L�O���x�Ƃ��j�̓v���~�G�^���ŁA�J�[�l�M�[�E�z�[���ł̃��C�u�B�Ȃ͒P���ŁA �]��ˊo�̂�����̂ł͂Ȃ����A���t���ւ�ւ�ł���B���A�����I�Ȃ����ɂ��u�h���}�e�B�b�N�E�\�v���m�v�ł���Alessandra Marc�����ەt�ŋC�ɓ������B�ޏ��̓V�m�[�|���ƈꏏ��Schoenberg�Ƃ���^�����Ă�������A�����o���Ă����̂�������Ȃ��B�����Koch�� �^�������A����قNJ��S������̂ł͂Ȃ��B
�@Lloyd-Jones�ɂ��Naxos�ւ̘^���͖w�ǂ��f���炵���B�e�B���g�i�[�̃u���b�N�i�[�ł��Ȃ��݂̃��C�����E�X�R�b�g�����h�����ǂ��ǂ��� ���o���Ă���̂����A�����Sudoku������Ă����̂�Bax�́u�k���I�ȁv���͋C�������Ȃ������B�[�����ȑ��ԁA��O�ԁB
�@�����Ⴒ���Ⴕ�Ă��āA��◝���ɋꂵ�ނ̂����A�˔\�����ȉƂł��邱�Ƃ͕������Ă���c�F�������X�L�[�̑�\��ł���A�w��������ȁx�ƃx���N�̊� ���y�Ȃ̃J�b�v�����O�B���ς�炸�́u�����v�i���̐l�́u���傢���v�Ȃ�Ă���Ȃ��j���₶�̃M�[���������A���������A�т��т��������̂ŁA�� ���������Ȃɂ͒��x�ǂ��B�V���C�[�̂悤�Ȍ�����}���h�ւ̃A�v���[�`�ł͂Ȃ��A�V����ւ̋��n���Ƃ��Ă̂��́B����́u��ΔՁv���B�i�� ArteNova�j
[�W���P�b�g���Ⴄ�B�N�����g���A�b�e���x�����H]
�@�����z�����C�U�[�̓}�C�i�[�ȋȂ��D�������A����ȏ�ɁA�I�P��������A��������}���Ă܂��ɐE�l�ł���B���qWagner��Siegfried���e ���Ɠ��l�A�����Ȃ��n�����ň�ȏ����Ă���B�˔\�̍��͖��m�����A�S�̂̓Z�܂肪�����B���}���h�̉��y�Ƃ������Ƃ͕�����̂����A�Ȃ�Ƃ������A�M���Ƒn �ӍH�v�Ɍ�����B�ق�̂�����Ƃ悢��������̂����E�E�E�B���łɂ��^���̂悤���B���A�x�������E���W�I�E���������̂��Ƃ��Ȃ�M���n�[���j�[���o�� �Ă�B�^�����ɏ�I�i��Koch�j
�@����w�������A�[�m���N�[���̃n�C�h���͗\�z�ʂ�̑f���炵���o���B�V�����Ƃ������A�قف[�A�Ɣ[�����Ă��܂��Ƃ��낪���X����B�A���X�e���_���E�R�� �Z���g�w�{�E�����h�ɃA�[�m���N�[���̎��u�ʂ�����v������Ă���B�c�O�Ȃ̂́A�R���Z���g�w�{�E�̃z�[���E�g�[���y��Warner�̗D�ꂽ�^�����A �����ł͂���������^����Ă��Ȃ��B�c�O���ɁB
���{���� �������y��
�@�� ���Q���x���N�w��ACO�@R.�V���g���E�X�F�w�p�Y�̐��U�x�A�wDon Juan�x�@��Teldec
�iTeldec�ɂ�� Telefunken��Historic�V���[�Y�̈�B�O�҂͏����ҋy�є팣��҂ł���B����ɂ��Ă����̕����肩�炷��ƃf�t�H�������܂���̂��̂� ���A�u�I�[�Z���e�B�b�N�v�Ƃ����Ӗ��ł͂��ꂪ�f�t�H���g�Ȃ̂ł��낤�B���������A�����Q���x���N�͐����B�ǂ̂悤�ȉ��y�ɂł������A�h���}�ƁA���w�� �ƁA�_�C�i�~�Y���ƃ��}����^���Ă����B�������A�K��ǂ���̘g�ɂ͂܂������̂ł͂Ȃ��āA�����̂�����Ȉӎ��A�v�z�������āB
�@���̉��t�́A�����̃��[�x������o�Ă��邩��A���ꂩ����_�u��Q�Ȃ�ʃ_�u�蔃���������������A���Ƀ_�u���Ă���B
�@����Teldec�̂�́u���K�Ձv���������āA�ʐ^���▭�ł���BTelefunken�ŏo�Ă���SP�Ɓw�p�Y�̐��U�x�̂����Ⴒ���Ꮡ�����܂ꂽ�X �R�A�ł���BSP�̕\�ʂɂ�Professor Dr. Willem Mengelberg�ƂȂ��Ă���B�j
�@�R ���h���V���w��ACO�@�����F���F�w�_�t�j�X�ƃN���[�G�x�A�J�b�Z���@��Philips
�i����łɂ��ACO�ƃR���h���V ���E���R�[�f�B���O�̈�BLive�Ŏc�O�Ȃ���A�I�P�̃R���f�B�V�������A�^�����[�Ђ����݂����[�ǂ��͖����̂����A�R���h���V���̋ϐ��̎�ꂽ�A���} ���e�B�b�N�Ȕ������f���炵���B���[��A��͂�A��C�̘^�����E�E�E�C�ɂȂ��Ă��܂��B�j
�@�A�b �J�[�}���w��PO�@J.�V���g���E�X�F�w��������x�@EMI
�i�B�ꂽ���Ղł���B�J���������A �x�[���A�}�^�`�b�`���A�����܂��A�N���C�o�[�̉��t���m��Ȃ��̂����A����́A���Ɂu���B�[�����v�̏�������o���Ă���B�e��Ƃ����F�C�Ɖ��A���N�� ��������ޔp�ƁA�ċz�́A���̎�Ƃ��ǂ��w���҂̍˔\�ł��낤�I�S�������Ș^���ƃ��}�X�^�[�B�j
die.17.oct. �@���Â肪�E�E�E�B���C���Ȃ̂����A���ꂪ�������������i���ɑ������̂悤�ȍ� �o���E�E�E�B����ɂ��Ă����̌��Â肢�������ɂ��Ă���B�O�\�H���Ȃ̂��H��Ȃ���A����̂����ȁH
���{���� �������y��
�@�x�[ ���w�����B�[�������̌���@R.�V���g���E�X�F�w�i�N�\�X���̃A���A�h�l�x�@��Koch
[Preiser�̃W���P�b�g]
�i����́A���B�[�������̌���̃��C �u�̃V���[�Y�ł���A���̂���Ӗ��ł��Ӌ`����L�^�ł���B�Ȃ����Ƃ����ƁA���̏㉉����1944-6-11�ŁAR.�V���g���E�X��80�̒a�����т��� ��u���Д��g�v�̈�Ȃ̂ł���B���炭�A����̓X�^�W�I�^�����Ǝv����قǗǍD�ȉ����ŁA���t�������Ԃ���̂��́B���ɂ��̎���̃x�[����R. �V���g���E�X�̗ǂ���َ҂ł���B�̎���@�����o��悤�Ȗʎq�ŁA���C�j���O�̃A���A�h�l�A���[�����c��Wagner��̃o�b�N�X�A�m�[�j�̃c�F���r �l�b�^�A�����ă[�[�t���[�g�̋ɂ߂��̉��y�ƁB
�@�^���������̈ꌾ�̑f���炵�����́B�����ł��I
���A�x�[���̓��Ȃ́A���ɓ��ӂɁ[�{���ɓ��ӂɁI�[���Ă������������āA�U���c�u���N�ł̃��C�u�A������65�N�̉f���A�����āA�o�C�G�����Ƃ̃X�^�W�I �^���[�������I�Ȃ�[������B�j
�@�ŋ߁A��L�̉f���ł́w�i�N�\�X���̃A���A�h�l�x�͂܂��Ă��܂��āA�����Ε����Ă���B�Ȃ����G���[�f�w��BPO�A�f���E�J�[�U��EMI�ւ̃X�^�W�I �^���A�����͏��X���ƌ������A�u�h�C�c�I���^�ʖڂ��v���ʔ����Ȃ��B
don.19.oct. �@�������ς�炸�A���{�ł͖��w���҂̕���������CD�����ϋɓI���B����� Kegel�B���������̃f�B�X�R�O���t�B�[�ɒlj����āAUp����B���������͖̂{���͖ʓ|�������̂����A�����ɂ��Ȃ��ƁA�d�����ǂ�ǂ܂��Ă����� ���܂��̂�������̂ŁA�������悤�ɐS�����Ă���B
���{���� �������y��
�@���@ ���g�w��NDR���@�u���b�N�i�[�F�����ȑ�ܔԁ@���T�Ł@��RCA
�iWand�̓u���b�N�i�[�����Ȃ̃} �C���X�g�[���Ƃ��āA���O���̌����ȑ�ܔԂƑ攪�Ԃ������Ă������A���ɂ����Ƃ��Ȃ��Ƃł���B���ɃV���t�H�j�b�N�ł���A�\�z�I�ł���A�h�C�c�E�I�[�X �g���[�̌�����}���h�̊j�������ɑ̌����Ă��邩�炾�B���ɁA�S�V�b�N�I�A�o���b�N�I�Ƃ��̂���邱�̃V���t�H�j�[�́A���̃X�P�[���̑傫���́A���̔ނ� ��ȁA�y�ё��̃V���t�H�j�X�g�Ɣ�r���đ��F������ǂ��낪�A�ō��̂��̂��Ǝ������Ă���B
�@���N�́ABotstein�̒��i�H�V�����N�ł��Ă��āA����܂��ʔ����������̂����A���́u�܂��Ƃ��ȁv���T�ł��܂��Ɍ��T�ł��낤���H���́A BPO�̔Ղ��A�ŋߏo���~�����q�F���E�t�B���Ƃ̃��C�u�Ղ������Ă��Ȃ����A��r�ł���̂��P�����̂��̂����A�����ł�NDR�̂͏���m������蕺�̃I�P �ŁA�C�S�����ꂽ���̂ł���A���d���ׂ��L�^�ł��낤�B
son.29.oct. �@10���Ԃ�̓o��B�ӑĂł���B�Ӗ��ł���B�p���͗͂Ȃ�I
�@EMI����o�Ă���Boult�w����Wagner�̊nj��y�W�͌������B���炭�ABoult�ɂ���A�^���ɂ���w�ǒ�������Ȃ����̂ł͂��邪�A�f���炵 ���I�ނ̗ǂ��_�́A���}���e�B�b�N�Ȕ����ƃX�P�[���̑傫�����t���B����ł��Ȃ���A�N�����y���[�̂悤�ł��A�e���V���e�b�g�̂悤�ł��Ȃ��ABoult �̂�Boult�̉��t�ł���B�ʔ����̂��A�c�̃A���T���u�������킹�Ȃ��A���킹�Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A�u�����ɂ�����炵���v������������̂��ꋻ�ł��� ���A�G�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����E���đ�����悤�Ȃ��̂ŁA�C�ɂȂ�Ȃ��B����NPO�Ƃ̂��̂����傾�B
�@���̐l�̂́A�}�[���[�́w���l�x�A�u���[���X�̑S�W�ł������������悤�ɁA�͂�����Ƃ��A�������Ȃ��Ƃ���ŁA�N�[�x���b�N�Ɏ��Ă���Ǝv���̂� ���E�E�E�A�ǂ��ł��낤���H
[�W���P�b�g�͈Ⴄ���B]
���ɂ͂Ȃ����p�Ղ̃��C���X�h���t�w��VPO��R.�V���g���E�X�F�w�i�N�\�X���̃A���A�h�l�x�iDecca�j�B���AVPO�Ƃ̋M�d�Ș^���A�w�h���E�W�� ���@���j�x�A�w�t�B�K���̌����x�������ɔp�ՁI�Ȃ�Ƃ����A�����̖����ł��낤���I
���{���� �������y��
�@�N�[ ���w��Orchestra Filarmonica Marchigiana�@R.�V���g���E�X�F�w�O���g�����x�i���Łj�@��ArteNova
�iRS�̌��h����I�y������ځB�� ���Ŕ������ɁA�e�N�X�g�t�A�I�P�A�^���ALive�ł̍��g��������A�Ȃ��Ȃ��ǂ����đf���炵���o���ł���B�j
�� [Top]