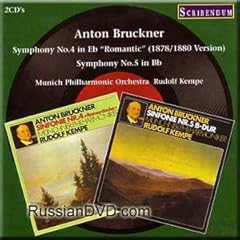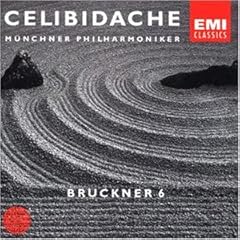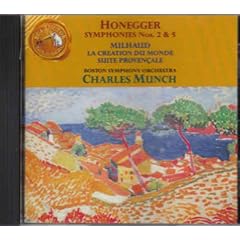"Und
morgen wird die Sonne wieder scheinen..."
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょ う・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日 頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
[Diary; Tagebuch; Diario; Journal; 日記]
「そして、明日も又太陽は昇るでしょ う・・・」という歌曲の一節からとったこの項は小生が日 頃何を聴き、何を考えているかを記す場所です。
|
[A.D. 2007 / Heisei 19 /
Kôki 2667] July; Juli [Last modification: 27.Jul.2007] |
mon.04.07. 七月になってこの寒さだよ。どうなってんの?。
七月より新しいことをやっているので、少々の緊張。
偉大なるアーノンクールのHPは|こちら|。
<今月購入した CD>
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:『天地創造』 独Warner 8.99E
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:『四季』 独Warner 9.99E
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:『天地創造ミサ』 独Warner 6.99E
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:交響曲第6-8 独Warner 4.99E
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:交響曲第30,53,69番 独Warner 6.99E
@アーノンクール指揮CMW ハイドン:交響曲第31,59,73番 独Warner 6.99E
@ベーツェル指揮シュターツカペレ・ヴァイマール室内管 ハイドン:交響曲第16-19番 独
Berlin Classics 1.99E
@ヨッフム指揮シュターツカペレ・ドレースデン ハイドン:交響曲第93-95.98番 独Berlin Classics 2.99E
@ヘルヴィッヒ指揮ベルリン響 ベートーヴェン:交響曲第三番 独
Berlin Classics 1.99E (ジャケット写真は新しいエディションのもの)
<本日聞 いた音楽>
アーノンクール指揮CMW ハイドン:交響曲第31番『ホルン信号』、59番『火事』、73番『狩』
(私は長いこと、こういう演奏をまっていた!素晴らしい、の一言。)
mon.09.07. 七月?寒すぎ。23時ちょい前の今、なんと13度。しかも、雨。異常。今までかなりベルリンに住んできたが、こんなに寒い七月は初めて。やっぱり、「世界異常気象」とかいうんだろうかね。
今月はハイドン月間?アーノンクールやらシンフォニーやらを中心に今まで聞いてきた。
アーノンクールのオラトリオはヴィーン響とのライブで、歌手を有名人でかためたものの、オケとの合致、及び独唱のオペラティック、そして、アーノンクー ルの「気合の入れすぎ」でかなりしっくりこなかった。テンポも通常よりかなり遅いし、少々オケをもてあましているかの感あり。これが、スタジオでじっくり つくられて、自分のオケであったならば・・・。残念ではるが、つまらなくはない。
今は、マリナーのハイドンやら、クイケンの『四季』やら、を聞いている。マリナーのは現在ではやや中途半端の感がなくもないが、小編成で爽やかに演奏するのはハイドンを楽しむ上では重要であろうか?
<本日聞 いた音楽>
マリナー指揮シュターツカペレ・ドレースデン ハイドン:ミサ曲 EMI
(昔 のシリーズの一つ。マリナーが珍しく、旧東のオケをしかも、名門ドレースデンをふった数少ない演奏。オケの渋さを、指揮者の爽やかさが絶妙にマッチした演 奏だと思う。ミスマッチだが、レパートリーによっては良いコンビかも。因みに、最初に買ったハイドンのミサ曲はこのCDであった。)
die.10.07. 寒い、未だセーターを着ている。今日は黒。ハイネックにあらず。
<本日聞 いた音楽>
カバスタ指揮ミュンヒェン・フィル ブルックナー:交響曲第四番 独Pilz
(PILZのジャケットは流石になかったので、Preiserのもので。)
(今は無き、PILZによる、不遇の指揮者カバスタのブルックナー。結構すっきりとしていながら、少々ロマンティックで、かつ暴れるところは暴れる不思議な名演奏。清潔さと見栄を張った「動的な」(わざとらしさ、にあらず)演奏で、時代を超越したものだと思う。
ジャケットでは、ライブらしきものー一発録り、1943-6-30−と書いてあるのだが、其れにしては、録音も明解だし、オケもかなりの高度なもの。
終戦時に自殺をしていなければ、更なる偉大な指揮者に化けていたであろうこの不遇な芸術家のよすがを偲ぶには絶好のCDであると思う。)
因みに小生のDiscographyは|こちら|。
son.15.07. ようやく、夏日到来!なんと、最高気温33度、でもって明日は37度予想。どうなることやら。
<本日聞 いた音楽>
シューヒター指揮?管 モーツァルト:『高級からの闘争』ではなく、『後宮からの逃走』抜粋 独EMI
(オー ケストラ名はないが、こりゃ、かなりのオケでしょう。BPOでもいいくらい。シューヒターのオペラ指揮者の面目躍如でー少々ドイツ的だがー実につぼには まったもの。歌手は当時の名歌手ばかり集めて、ベルガー!、ショック、オットー、ウンガー、フリックという錚々たる面子。モノーラルで、ややキンキンする が、それ以外は優秀すぎるほど。ヴィーン風だけがMozartではありませんな。)
ブロムシュテット指揮ベートーヴェン:交響曲 独BerlinClassics
(大 よそ約5年ぶりの再聴。で、かなり印象が変わった。これはかなりレヴェルの高い演奏ではないですか!ブロムシュテットのやや強引だが、他の意味では力強い マッチョな演奏、でも、オケは優雅で、この微妙なミスマッチが面白い。特に、八番は久しぶりに感銘を受けた名演であった。)
mon.16.07. 暑くて寝られん。しかも、今年は雨が多かったために、蚊の大量発生。こりゃ、異常。
うとうとしかけている時に、ぷーん、とくる、例の蚊の音。これに参って、寝られませんわな。睡眠もやや不足気味。
尚、日曜日は34度。でもって、月曜日は37度くらいあったもよう。
暑さも蚊も勘弁してくれ。
なかなかセクシーな写真。ベルリンより。因みに、これ、dpaがソースだが、多くの新聞、ネットで使われている。
<本日聞 いた音楽>
カンガス指揮Ostrobothnian室内管 Per Norgard:弦楽オケのための作品全集 フィンランドFinlandia
(な んか、全般お化けのような音楽の集大成。一応現代音楽みたいだけれども、なんかなぁ、つかみどころが無い。1932年生まれで、シンフォニーとかも書いて いるみたい;ま、全然分からないけれども、ジャケットくらい載せておきますわな。どうせ、この先何年も聞かないであろうから。)
son.22.07. 暑いんだか、寒いんだかよう分からない気候。今日はまたまた涼しくなりやがって、夜である今は14度。ちょっとねぇ、秋が来るのには早いのでない?
最近は、オケの音色の違いを楽しんでいる。そうなるとやはり、シュターツカペレ・ドレースデンか?
<本日/最近聞 いた音楽>
ベーム指揮S.D. R.シュトラウス:『エレクトラ』 独DG
(渋 いながらも、「音楽」のもつ魅力やら、オケの音色、管弦楽法の味わいを十二分に示している隠れた名演。Soltiの盤に隠れているが、作曲家の表現したい ものでは、やはりこちらの方に軍配が上がるのではないか?1960年の録音だが、音響が良いLukaskircheだし、歌手も葬送たる面子を揃えてい る。『エレクトラ』という作品_そのもの_を「楽しみたい」のであれば、この記録はイチオシである。
ベルグルンド指揮S.D. スメタナ:『我が祖国』他 EMI
(残念ながらEMIのforteシリーズの写真がなかったので、代替として)
(何を勘違いしたのか、この曲を最 初の盤はこれだし、正直、全体としては、それほどこの曲が好きではないので、これが唯一の「参考盤」となっている。ベルグルンドはWandのように、かな りドライブする指揮者だが、一見だるい、S.D.のオケをかなりびしびし激励しているかのようで、一瞬面白みのある演奏であるかもしれない。)
ムラヴィンスキー指揮レニングラード・PO チャイコフスキー:後期三大交響曲 独DG
(天 下周知の名レコード、らしい。最初に聞いたときにはそれほど、正直感動しなかったし、スタジオ録音のマイナス点である、ある種の緊張感・躍動感が失われて いるような気がした。二度目の今回は、そういうマイナス面をかなり克服できたし、かなりレヴェルの高い演奏であることには依存が無い。だが、「私の」チャ イコフスキー後期三大交響曲は、他のにしたいと思ったしだい。決して悪い演奏ではないのは分かっている・・・。)
ケンペ指揮ミュンヒェン・フィル ブルックナー:交響曲第四番・第五番 独PILZ
(PILZ盤のがないので、違うものを)
(ミュンヒェン・フィルは最高のオケでもないし、ケンペの最高級の指揮者ではないーと私はー思っている。だが、この演奏に関してだけは、最高の賛辞を送り たいと思う。とにもかくにも、自然体でありながら、抑えるべきところはばっちり決っている上に、嫌味が無い。それでいて、味わい、また、独自性、特に弦の 爽快さ・透明感、清潔さには感服。最後の高揚感とか、深い味わいも貴重である。何はともあれ、この曲が好きな人には「絶対」聞かなければならない演奏であ ろうことは、間違いない。
天晴!)
don.26.07. 体調最低。お腹の調子すこぶる悪し。食欲、意欲殆ど無し。
音楽もそれほど聴く気合がないのだが、シュターツカペレ・ドレースデンを楽しんでいる/た。
<本日/最近聞 いた音楽>
ベーム指揮S.D. R.シュトラウス:『バラの騎士』 独DG
(ベー ム唯一のスタジオ録音で、後は後年のザルツブルクにおけるライブがある。正直言って彼の、R.シュトラウスの演奏は、やや乾きすぎたり、そっけなかった り、こくやら味わいやらが錆び切っている感じがして、曲によってかなり印象が違う。このドレースデンの演奏も長いこと鶴首してその発売を待っていたのだ が、その演奏の荒さ、録音の酷さ、リマスターのできの悪さに辟易した覚えがある。
よって、再聴の今回は実に、5年ぶりである。第二幕からようやく、音がクリアーになってくるものの、指揮者ベームの生真面目さが悪い意味で裏目にでたよ うな感じだし、ドレースデンのオケのその芳醇な響がかなり失われているのは残念至極である。この当時の競合盤は、EMIのカラヤン、DeccaのE.クラ イバーだが、私はその中では総合的にカラヤンのが好きだし、推したい。
歌手では、当時三十台前半とは思えないほどの、F.-DieskauのFaninalや、シュトラウス歌いのSeefriedのオクタヴィアンが良い。 オックス歌いである、ベーメはやや真面目すぎるかな。シェヒの元帥夫人は_かなり_年をいった元帥夫人であって、これまた、枯れている。)
バルビローリ指揮ハレ管 ベルリオーズ:『幻想交響曲』他 蘭Disky
(待ってましたのバルビローリ節満開の演奏。オケのへぼさはなんのそので、こってり、かつ情熱的に歌うのは良いし、カップリングの小品も立派過ぎるほど立派。)
ロジンスキ指揮PO、RPO artist profile EMI
(ドライで、いかにも当時のアメリカ聴衆に受けたであろう、ばりばりーばしばし型のスパルタ指揮者である。そのダイナミズムと明解さはかのトスカニーニに通じうるであろうか。しかしながら、シュトラウスの『クープラン舞踏組曲』における、真面目な清潔さは好感が持てる。)
(ここから本日分)
チェリビダッケ指揮ミュンヒェン・フィル ブルックナー:交響曲第六番 独EMI
(チェ リのブルックナーには様々な思いがある。長いだけ、大風呂敷を広げただけ、間延びしただけ、CDで聴くようなものではない・・・。だが、その中にいくつか は「聴くに耐える」ものがあり、更に素晴らしいものがあるのも事実。この「小型」、「日向」のような六番は、チェリにしては比較的テンポも速いし、それゆ え緊張感も持続していると思う。オケの透明さは良いものの、味わいに乏しいし、管も抜群とはいえがたいが、第六演奏の中でも、優れた解釈の一つであろ う。)
ミュンシュ指揮ボストン響 オネゲル:交響曲第二番、第五番 ミヨー:『プロバンス組曲』、『世界の創造』 米RCA
(手 練手管のものとはこういうもの。アメリカのオケの機動力、とフランス指揮者の絶妙なマッチが、実に気持ちよい。陰気なオネゲルだが、なかなかに面白く聞け るし、ミヨーの二つの組曲はステレオ録音という条件も相俟って、ミュンシュの「艶気」と作品の「面白さ」が爆発している。)
▲ [ Top ]

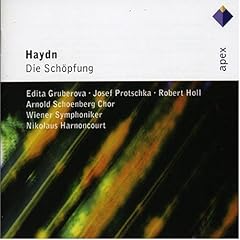

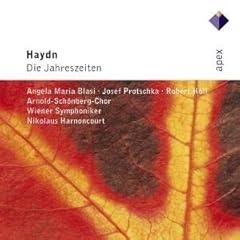


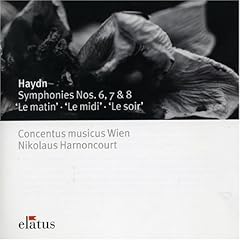


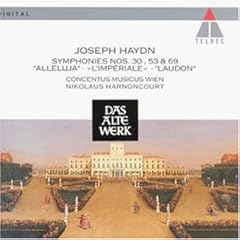
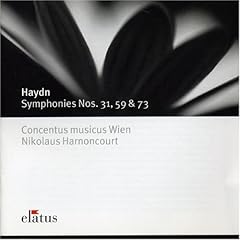



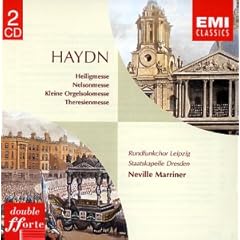
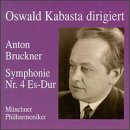
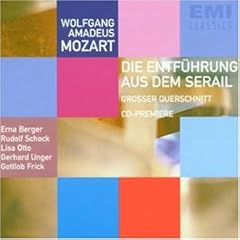
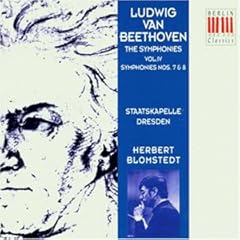

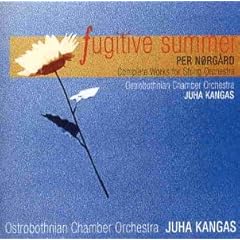
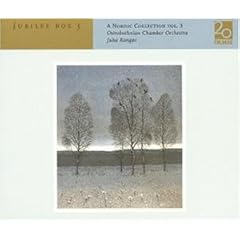
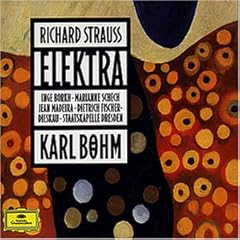
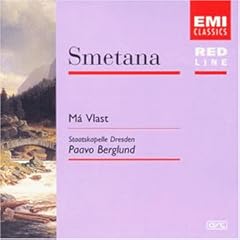
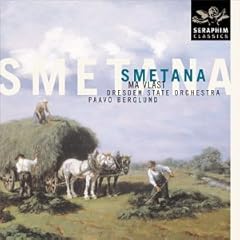
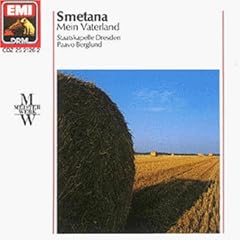
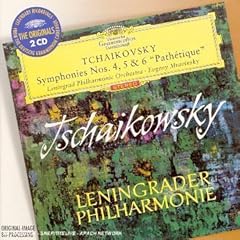
![Tschaikowsky: Sinfonien 4, 5 und 6 [Doppel-CD]](http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/61BT2XM3FNL._AA240_.gif)