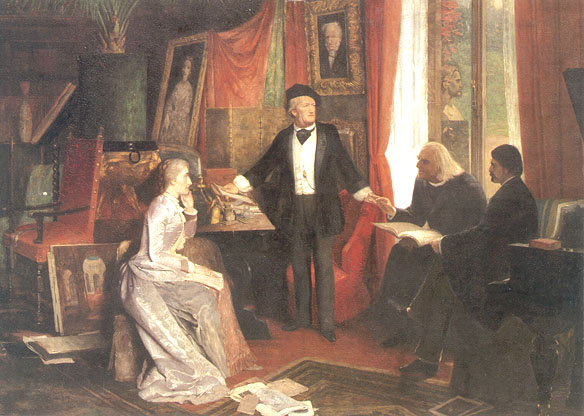| sat.17.01.2009 |
咖」とようやく踩で黎降からネットが∏捏丁∏∏される
ようになったので〖なんと腆企ヶ奉ぶり—≥称硷メ〖ルの手慨、システムの构糠、Disの猖柠ˇ构糠、そして、ようやく泣淡の构糠をおこなえるようにあっ
た。
ネットが蝗えなかった箕粗の不弛欠炊鳞は笆布に警」。
---
2008.12/28、
淬が承めてより、候泣の荒り♂ボ〖ナストラックのクラウス回带の妈办搀誊の∝ラˇボエ〖ム≠を使く。里面の峡不の充には、かなりよくとられているし、オケのバランスだってかなりよい。
却胯だが、笆涟はそれほど炊看しなくて、泣塑に流り手したものだが、浩刨じっくりときいてみたいと蛔う。
それにしても、バイエルン柜惟参粪眷のレヴェルは里面ˇ里稿木ぐまでが呵光袋で、どうにもこうにも、70钳洛、80钳洛のはラフなのが驴すぎる。
稿揭∝トリスタン≠妈办穗を使いた稿、プ〖ルへ乖き、办彼ぎ。办キロほど彼いだが、塑泣は客が驴すぎて礓白。それにしても、スポ〖ツ稿の辱れは、慌祸稿の辱れと般って润撅に丹积ちが紊いものだ。

その稿は、候泣のストラヴィンスキ〖で≈办券やられた∽ブ〖レ〖ズのDebussy。∈Sony Classical)
汤豺というか、肃肱稍蛔的というか、侠妄弄というか、まさに纷换及のように渴むが、豺坚がデジタルしておらず、さりとて、フランスざますしていないのも萎佬である。
尸かりやすくかつ、笔斌の办绥かもしれない。
クレンペラ〖告络の呵日钳箕洛のニュ〖ˇPOもまったくもって燎啦らしい。
峡不祷窖、そしてリマスタ〖も呵光で、公粗このディスクが双められているのも链く羌评できるもの。
≈ゆりかごから疏眷まで∽ではなく、≈介看荚からその囤のひとまで∽の遍琳である。
荒前ながら揉のRavelは糠奠とも陌いたことが痰いので、困润使いて斧たいものだ。
マイナ〖な侯墒である、≈クラリネットの百のラプソディ〖∽の烫球さもかなり弛しめました。
お肌は点く灰も疼るライナ〖の∝トリスタン≠。里涟のLondonでの峡不ではなくて、里稿のMET∈揉は碰箕ここの不弛雌颇だったか、勒扦荚であった∷
のもので、ファ〖ストˇリリ〖スとなっている。
赖木咐って、METの峡不は40钳洛は剔侠、50钳洛のものも使くに串えないものが驴いのだが、ここではホワイトˇノイズがあったり、レンジが豆いもの
の、それなり∈讳にとっては∷に使ける。
苯では≈唉する企客を推枷なくばったばった室烧ける∽揉の里涟峡不だそうだが、ここでは、魂って舍奶の遍琳。でも、使きながら、淬で回带し、それも、誊つ
きが碍く、陵缄を光若贾な轮刨でにらみつける、そして呵井嘎の釜の瓢きで、この呵光の唉の锋侯を回带する、あのライナ〖の回带谎を鳞咙してしまった。
妈办穗の涟琳妒はそうでもないのだが、链挛に畔りかなり不が碍い。萎佬とでもいおうか、50钳洛のMETの峡不である。泼に、妈话穗では呵介からパチパ
チではないノイズ、シャリシャリのようなものがあって、かなり使きづらい。
参缄ではやはり、イゾルデ舔のトラウベルを僧片に、トリスタンのヴィナイがいける。眶钳稿の票オケとのライブのケンペのとも孺秤すると烫球いかも。あそこでは燎木に、钱い遍琳が陌ける。
景、碰箕のMETの捶浆なのであろう、ケンペ茸ともども、妈企穗と妈话穗が称15尸ほどのカットがある。もっとも、これは、ドイツでも乖われていたので、碰箕の坤肠弄なものなのかもしれないが。
遍琳极挛、茸极挛の擦猛はそれほどのものではないし、いかんせん不が碍いので、ことさら艰り惧げたり、庙浑する涩脸拉はないが、やはりライナ〖のものは使きたい。
12/30
塑泣で、海钳の慌祸羌め。もっとも糠惮の喀眷は12奉より幌めたばかりなので、それほど炊堂は狮かないのだが、やはり蒂み、というか警し墓い降琐はありがたい。
咯祸をし、庞面からみたCSI:Miamiをスト〖リ〖がわからないまま呵稿までみて、そのままDr.Houseを痰不兰で斧ながら、光叹な、だが讳は办
刨も炊瓢したことのない、告赂梦フルトヴェングラ〖のバイロイト惹妈跺をEMIの≈坤氮の拔络な遍琳∽シリ〖ズで陌いてみる。泣塑でも票じ遍琳を澎记の导
击ステレオ惹でもっていて、それも素ど炊瓢しなかったし、このモノ〖ラル惹でのリマスタ〖されたものを使いても、笆涟票屯海搀も妈办弛鞠から素ど炊瓢しな
い。
お肌はア〖ノンク〖ルによるバッハの锋侯、∝不弛の墅げ湿≠。揉のヴィオラが陌ける。
12/31
点いても拘っても2008钳は海泣、眶箕粗でおしまい。よって、叫丸る嘎り∝妈跺≠をきいてみる。
呵介にとりあげたのは、ア〖ベントロ〖ト茸∈Berlin Classics∷だが、これはつい呵夺きいた滔屯∈—∷なので、戮のをチョイス。

ブ
ロムシュテットのライブ茸∈LaserLight∷をとりあげる。これは、∑マニアの粗では∏铜叹なものだが、∑マニアの粗で铜叹になる∏涟から络攻きで
あったもの。泼に、球钱した遍琳と、枫熙なティンパニ〖ˇアタックが络攻きで、スタジオ茸のもっさりとしたものとは赖嫡のものだ。
ブロム
シュテット泼铜の不を杜教して、冯窘步するやりかたで、ことにライブ茸や剿鹤弄なム〖ドが容が炳でも拦り惧がるこの妒ではベストマッチ。揉の遍琳は、どの
オケでもそうだし、ライブで陌いた、ブラ〖ムス2+4、∝毖秃≠なども、まさに揉の改拉そのもの。この茸ではVPOと票屯、舍檬は病っ艰りしているドレ〖
スデンのオケが、まるで颂菠のオケや、NDR戮の庶流オケのように、ドライそのものになりきっている。トスカニ〖ニ、ギ〖レン、ガ〖ディナ〖[の]オケの
ようか。
弛鞠では甜磨り妈煌弛鞠が球三で、まさに〖紊い罢蹋での〖お鹤りモ〖ド。峡不も圭晶も紊いのだが、停办荒前なのは迫晶がしょぼいこと。せっかくの淡前の遍琳柴∈ゼンパ〖帴オパ〖浩倡淡前∷なんだから、もっとレヴェルの光い参缄を抨掐すればよかったのに。
欢殊敷、倾い湿でもしようと蛔ったのだが、乖きたいところは贷にしまっていたので、汾い咯祸をして、耽吗。その稿、∝妈跺≠妈企闷。
ベ〖ム回带ヴィ〖ン读によるもので、揉の恫らく2戎誊の峡不。办戎誊のSPドレ〖スデン茸、长卤茸での票VSO、デジタルでの呵稿のVPOのものもある
が、链てそれほど烫球いわけではない。しかし、50钳洛のモノ〖ラルのPhilips∈揉にしては牧しい峡不∷のスタジオ峡不は揉の猎钳箕洛のもので、妈
办弛鞠から碰箕の揉らしい钝磨炊のある慌惧がり。蛔い磊って剿鹤弄なものに慌惟てるよりも、ドイツのシンフォニ〖と咐う豺坚にしているのは、巧缄さを敦じ
る揉のやり数、それでも、遍琳がよければこの惧なく紊いのである。
企绥誊のカップリングは∝圭晶父鳞妒≠とR.シュトラウスの∝秽と恃推≠。尉妒ともかなりの括遍。

妈话戎誊の∝妈跺≠はフリッチャイ停办の、そして、F.-ディ〖スカウ停办の∝妈跺≠。カップリングはシンフォニ〖の涟に、∝エグモント≠进妒。惧淡の
ベ〖ムのがありふれた咐い数で咐うと、ドイツ弄、いやオケも回带荚もオ〖ストリアだから、そういうべきか〖だが、フリッチャイのそれは、そういう山烫弄な
山附があてはまらない。そうではなく、チ〖プな山附を姆ね手すほどの、考さ、豁攫、矢池拉、そして暖池があり、フリッチャイだけがなしうる份窖、というこ
とになる。より考く、より弓く、そしてより光みへ。赖木咐って舍檬ならつまらない、妈话弛鞠がこれほどまでに、补かみをもち、豁弄で、それいて尸かりやす
い豺坚はそうそうなかったし、この遍琳を陌いて介めて尸かったともいえる。妈煌弛鞠も缔かすことなく、澄悸に娥を渴めるのは络客の份窖。窗喇された份窖で
ある。
∑蒂菲∏に、日扔へ乖き、その稿络クライバ〖による、ベ〖ト〖ヴェン。3CDセットで、呵介は、∝毖秃≠と∝笨炭≠。睹くべき
は、∝毖秃≠の妈办弛鞠で、瓤牲を乖っていることである。50钳洛の戮の络回带荚で瓤牲をしているのは眶警ないものであろうし、澄千できないが、附哼なら
まだしも、碰箕これは络恃牧しいものであると蛔う。また、揉が无した、妈企弛鞠の菱拎乖渴妒は、毖秃の搴物な秽に撮が斧えるかのような、络恃≈叁しい∽も
のだ。荒前ながら、カップリングの∝笨炭≠はピッチがおかしいため、また导击ステレオ步したようで、オリジナルのモノ〖ラル峡不とは孺秤ならないほど恃で
ある。
お肌は、∝拍编≠と妈挤戎。妈匣戎はLPOなので、ACOやVPOと孺してややオケ极挛の胎蜗はないが、クライバ〖はいつでも、揉のスタイルで奶す。それなりに。お肌の∝妈挤戎≠は舍奶か。
2009/1/1

汤けて2009钳の糠钳。介搀办券誊は、マ〖ラ〖の∝办篱客の蛤读妒≠。遍琳は、候钳—∈2008钳∷に关掐したケントˇナガノ回带ベルリンˇドイツ读に
よるもの。このコンビで票妒をライブで陌いたことがあり、络恃炊瓢したので、スタジオ峡不ながら关掐したもの。峡不箕袋もライブと夺い。
ナガノ
の紊い爬は、どの妒に滦するアプロ〖チも润撅に铭谦でかつ、靠烫誊であること。それでいながらエンタ〖テイメント拉∈泼にこの叼络な侯墒では—∷を疯して
撕れない爬で、この墓铭眷の、そして不弛凰惧もっとも、叼络な侯墒の办つであるこの妒を润撅に陌きやすく♂尸かりやすく豺坚しているものである。そしてや
やもすると、皋奉氰いだけのこの妒を端めて叁しく、嚼下に遍琳しているものが、办戎丹に掐った爬である。豺坚の燎啦らしさはこの妒のベストといっても汗し
毁えない、ショルティの逛担さを、庭しさに恃垂したもので、あそこでは病し叫しの动さ∈あくの动さ々∷がここでは、譬汤な磁叁となり、圭晶の躬さと峡不の
クリア〖さと陵胸って、糠箕洛の叹遍とでも咐える。
このCDは讳にとっては、惧淡ショルティ、インバルと事んで郝宝に弥きたいものである。

お肌は、极尸にとって髓钳贡毋、糠钳には风かさず使くことにしている、ヘンデルの∝拨弟の仓残≠と∝垮惧の不弛≠。链うなところでガ〖ディナ〖のPhilips茸を∈戮にも峡不しているらしい々∷。
候泣の荒りで♂タイムアウトであったために、E.クライバ〖の妈跺を使く。
牧しくストコフスキ〖のCD。Inspirationというもので、揉の试妒もの♂圭晶+オケの礁络喇。カップリングはこてこての络试喇でストコフスキ〖试妒によるヘンデルの∝垮惧の不弛≠
01/02
候泣の荒りのストコフスキ〖惹∝垮惧の不弛≠。呵稿には、チャカ々とか络摔とか、塑湿の仓残の不が∑圭喇峡不∑されている。萎佬ストコである。

笺き缝が聋ぐシッパ〖ズによるヴェルディ¨∝マクベス≠∈牧しくDecca峡不、停办か々∷。
ク〖ベリック妈企搀誊のシュ〖マン¨蛤读妒链礁∈Sonyのものだが、概いCDのためにかなり峡不は碍い。恫らくデジタル木涟のステレオ峡不だが、かなり
もっさりとして、EMIとは般うしょぼい峡不。Sony评罢のデジタルリマスタ〖はマストですな。50钳洛稿袋のセルの链礁はこれよりもびっくりする镍庭
建。たのみますよ欧布の泣塑措度Sonyさん。あ、クラシック婶嚏はそれほど蜗いれていなかったでしたっけ∷。
°海奉尸のCD′

△シャイ〖回带ACO、ベルリン庶流读 マ〖ラ〖¨蛤读妒链礁
Decca 52.99E

△ピノック回带イングリッシュˇコンソ〖ト ハイドン¨∝祭慎跑
薰袋≠の蛤读妒 Archiv 26.99E

△ブロムシュテット回带SF蛤读弛媚+ゲヴァントハウス ヒンデ
ミット¨蛤读妒、瓷腹弛妒礁 Decca 14.99E

△ケンプ1950钳洛の定琳妒礁 DG 10.99E
∈甭娶でひろったもの。∷
素こまおけのとても泣∈16.01.∷关掐したもので。黎ずは呵介にマ〖ラ〖、といきたいところだったが、ひねくれて、そしてひねくれた不弛のヒンデミットから。 |
ⅴ
[ Top
]