自分で勝手に2006年に購入したCDのアカデミー賞
private
academy-award 2006

| ち
きちき第二回! 自分で勝手に2006年に購入したCDのアカデミー賞 private
academy-award 2006
|
|
| 01.01.2007現在 |
 |
Conductor Prize Nikolaus Harnoncourt. Royal
Concertgebouw Orchestra. Haydn Symphonies 68 & 93-104 Warner Nikolaus Harnoncourt. Royal
Concertgebouw Orchestra. Haydn Symphonies 68 & 93-104 Warner  どの曲、どの時代、どのオケとのものでもアーノンクールの演奏は何時でも刺激
的だ。それが、決して納得しなくとも、興味深いのは認めなければならないし、こういった孤高の芸術家は尊敬に値する。私は彼のMozartをそれほど知ら
ないし、比較的最近になってから彼の演奏を聴き始めたが、やはり彼の解釈が一番はまっているものの中の一つはハイドンであろう。ハイドンのはバッハのそれ
と違う意味で懐の大きい包容力のあるものだ。それ故に、その偉大さゆえに、決定的なハイドン演奏はなかなかないのも現実。しかし、アーノンクールのもので
聞
くと、ハイドンが丹念に作曲した、彼一流のオーケストレーションの珍味というか、妙を他の解釈からでは味わえることが出来ないほどに、聞けるのである。 どの曲、どの時代、どのオケとのものでもアーノンクールの演奏は何時でも刺激
的だ。それが、決して納得しなくとも、興味深いのは認めなければならないし、こういった孤高の芸術家は尊敬に値する。私は彼のMozartをそれほど知ら
ないし、比較的最近になってから彼の演奏を聴き始めたが、やはり彼の解釈が一番はまっているものの中の一つはハイドンであろう。ハイドンのはバッハのそれ
と違う意味で懐の大きい包容力のあるものだ。それ故に、その偉大さゆえに、決定的なハイドン演奏はなかなかないのも現実。しかし、アーノンクールのもので
聞
くと、ハイドンが丹念に作曲した、彼一流のオーケストレーションの珍味というか、妙を他の解釈からでは味わえることが出来ないほどに、聞けるのである。響きといい、ハーモニーといい、ウィットといい、どれもが説得力のあるもので、彼ら、即ち創造者である作曲家と再創造者である指揮者との見事なコンビ ネーション、チームワークを感じさせられる代名詞であろう。 表面より中身。体裁よりも真実。心地よさよりも問題提起。妥協よりも孤高。といったところか? オケのアムステルダムも指揮者の薫陶宜しく、普段の彼らのレガート気味でふくよかな柔らかさのハーモニーよりも、とげとげしているのも天晴れに尽きる。 購入時のコメント。 (まってましたの、アーノ ンクールによるハイドン。彼のデフォルメした解釈を聞くにつれて、思わずにやっとしてしまうし、ハイドンのそれはバッハとは違うものの、解釈の枠が幅広 く、包容力が大きいものの、それゆえに酷い指揮者にかかると、それは陳腐なものになってしまうのが恐ろしい。 しかし、アーノンクールの手にかかると、まさに水を得た魚のように、飛び跳ねる、びっくりさせられる、喜びを与えてくれる、楽しみを分かち合ってくれる という風で、まさにハイドンを聞いている気持ちがしてならない。  Nikolaus Harnoncourt. Royal Concertgebouw Orchestra.
Brahms Violin Concerto, Double Concerto Teldec Nikolaus Harnoncourt. Royal Concertgebouw Orchestra.
Brahms Violin Concerto, Double Concerto Teldec  聞き手に、「ロマンティック」とはなんぞやと、考えさせてくれる一枚。アーノ
ンクールやクレーメルは決して、こてこての旧態依然のロマンを求めていない。しかし、そこには、一種のクレンペラーに通ずる「ささや
かなロマンの炎とドライな情熱」とでもいった趣を呈している。最初聞く前には、アーノンクールがどれほど後期ロマン派の代表作曲家であるブラームスを捌く
のか、興味半分、恐れ半分あったのだが、聴いて正解。今までのブラームス像を簡単に引き剥がし、彼らなりのブラームス像を作り上げた。そこにはフレッシュ
さと、ロマンを否定しない、再創造としてのアーノンクールのロマンを感じた。 聞き手に、「ロマンティック」とはなんぞやと、考えさせてくれる一枚。アーノ
ンクールやクレーメルは決して、こてこての旧態依然のロマンを求めていない。しかし、そこには、一種のクレンペラーに通ずる「ささや
かなロマンの炎とドライな情熱」とでもいった趣を呈している。最初聞く前には、アーノンクールがどれほど後期ロマン派の代表作曲家であるブラームスを捌く
のか、興味半分、恐れ半分あったのだが、聴いて正解。今までのブラームス像を簡単に引き剥がし、彼らなりのブラームス像を作り上げた。そこにはフレッシュ
さと、ロマンを否定しない、再創造としてのアーノンクールのロマンを感じた。曲では、「駄作」であるところの二重協奏曲がこれほどまでに、面白く聞けたのは初めてだ。特にチェロのCelemns Hagenは指揮者、ヴァイオリニストと異種であるが、その繊細さには一本やられた。流石である。兎に角、面白い一枚でした。  Otto Klemperer. Daniel Baremboim.
Beethoven: Piano Concertos etc. EMI Otto Klemperer. Daniel Baremboim.
Beethoven: Piano Concertos etc. EMI  今年はベートーヴェンのピアノ協奏曲の当たり年で、このクレンペラー+バレン
ボイム盤の他には、アーノンクール+エマール、シュタイン+グルダがそれぞれ独自性を出していて聞いていて、なるほどと思わされた。 今年はベートーヴェンのピアノ協奏曲の当たり年で、このクレンペラー+バレン
ボイム盤の他には、アーノンクール+エマール、シュタイン+グルダがそれぞれ独自性を出していて聞いていて、なるほどと思わされた。特に、注目は『皇帝』。其のいずれもが、『皇帝』という陳腐な名を剥がし、曲のみで勝負しているものである。クレンペラー盤のは「宇宙の総支配人」、 アーノン クールのは「不戦派」、シュタイン・グルダのは「ジーンズを履いたナポレオン」のような演奏である。  Hebert Kegel: Legendary Recordings
Berlin Classics Hebert Kegel: Legendary Recordings
Berlin Classics  Kurt Sanderling: Legendary
Recordings Berlin Classics Kurt Sanderling: Legendary
Recordings Berlin Classics Bach Prize
 Helmut Müller-Brühl. Kölner
Kammerorchester Bach: Matthäuspassion Ger. Naxos Helmut Müller-Brühl. Kölner
Kammerorchester Bach: Matthäuspassion Ger. Naxos  私は言うまでも無く、バッハの大ファンだし、『マタイ受難曲』は新旧かなり聴
いてきた。それに、一時期はまっていたせいもあって、この曲は他の多くの曲と同じく、いつもいかなる録音も注目している。 私は言うまでも無く、バッハの大ファンだし、『マタイ受難曲』は新旧かなり聴
いてきた。それに、一時期はまっていたせいもあって、この曲は他の多くの曲と同じく、いつもいかなる録音も注目している。で、これがビンゴの演奏がこのNaxos盤。ドイツ国内向けの?もので、ドイツ語以外にはかかれていないもので、Das Meisterwerkシリーズの一つ。 私の『マタイ受難曲』のプレゼンス盤はコープマン、後はマウアースベルガーであり、それがバッハだと刷り込まされてきたし、良し悪しは別として私の大好 きな演奏である。それを更に新しくて興味深い演奏が今年一つ加わった。 この曲はどうしても、『肩肘張って』、『気合と思い入れをこめて』やるのだが、この演奏はそういった悪い意味での気負いが無い。あのコープマンよりも楽 々としていて、軽い。それでいながら、おちゃらけやあっけらかんな所が無い上に、指揮者がドイツ人で演奏家がドイツ人というのも驚く。 実によく流れるし、響きが明るく、実にポジティブで、抹香臭くない『マタイ』なのである。しかも、通常とは違ったオケのバランスというか、響きが聞こえ てきて、今まで培われた自分の中の『マタイ』像が崩れる、というか、こういう別の解釈があるのかと妙に納得してしまった。例えて言うとチェンバロではな く、フォルテピアノのようなバッハである。 決して腑抜けではなく、今までのアンチテーゼといってよいかもしれない。ご存知の!Naxosの録音の加減でこういった感覚が生れたかもしれないし、実 にふわふわしたような録音であるのは否めないのだが、デジタル金属臭した録音ではない。 歌手では、エヴァンゲリストのvan der Meel及び、イエス役のRaimund Nolte、アルトのMarianne Beate Kiellandが優秀。残念で、録音をぶち壊しているのはバスのHanno Müller-Brachmannである。これさえ無ければ・・・。 [Reference Discs]
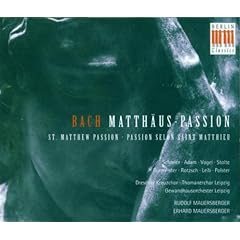 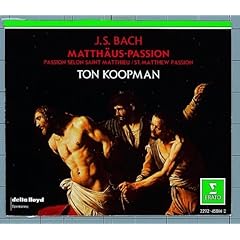  Collegium Aureum Bach: Vier
Ouvertüren (Suiten). Ger. DHM Collegium Aureum Bach: Vier
Ouvertüren (Suiten). Ger. DHM  録音は1969年。時代的には今から考証するとやや中途半端な時期で、「現代
やられているよう」古楽器でもなく、大編成でもない、所謂室内楽演奏、小編成でのもの。だが、初期の古楽器による「暖かさ」というか、「音楽の土台」を
しっかり構築する辺りには、時代や場所を越えて大きく説得力を持つものだ。そこには、ただ音楽に対する真摯さと、音楽だけの枠組みが出るような音楽家の配
慮が効いていて尊敬に値するものである。それは、ベルリン・クラシックスのヘルムート・コッホ盤にも通じる。 録音は1969年。時代的には今から考証するとやや中途半端な時期で、「現代
やられているよう」古楽器でもなく、大編成でもない、所謂室内楽演奏、小編成でのもの。だが、初期の古楽器による「暖かさ」というか、「音楽の土台」を
しっかり構築する辺りには、時代や場所を越えて大きく説得力を持つものだ。そこには、ただ音楽に対する真摯さと、音楽だけの枠組みが出るような音楽家の配
慮が効いていて尊敬に値するものである。それは、ベルリン・クラシックスのヘルムート・コッホ盤にも通じる。録音は、リマスターのお陰でびっくりするほど良い。元々が良いのか、それとも技術によるものなのか?何れにせよ、素晴らしい演奏を、素晴らしい録音で。 尚、同じ団体によるブランデンブルク協奏曲も美演であった。 購入時は以下のコメント。。。 (正直言って、全く期待をしないで購入したもの。だが、しかしである。これは最高の意味で裏切られた。年代が69 年なので、演奏も中途半端で録音もへろだと思っていた。が、一言でこの演奏をいうなれば、実に愉悦を感じる演奏だ。音楽家がドイツ語の言うところの Musizierenをしており、合奏をしているのだ。音楽を聴く、という行為は人それぞれ違った意味で楽しむのだが、この演奏を聴いていると、作曲家の 芸術を手に取り楽しんでいる様子が分かる。こういうのはなかなかお目にかかれないのが現状だ。演奏も実にお見事。60年代後半であれだけの演奏が出来れば 優秀だ。最近の演奏、特に古楽器の演奏はその過激さゆえや、学究的だけで、音楽を聴く楽しみに欠けたものが多いのだが、これは丁寧で宜しい。録音もリマス ターが異常にクリアーになされており、楽器と楽器の間の呼吸が聞こえるかのようだ。今まで聞いた同曲の中で最高の演奏であった。) Beethoven Prize  Horst Stein. Friedrich Gulda. Wiener
Philharmoniker. Beethoven: Klaviersonaten u. Klavierkonzerte Ger. Decca Horst Stein. Friedrich Gulda. Wiener
Philharmoniker. Beethoven: Klaviersonaten u. Klavierkonzerte Ger. Decca  聞いたときのコメント 最近はまっているのはグルダのベートーヴェン。特に、『ハンマークラヴィーア』の第四楽章!凄まじい。ピアノは バックハウスと同じく、ベーゼンドルファーのインペリアルを使っているはず。でも、雰囲気が全くといってよいほど異なっている。グルダのは少々右手、即ち 高音がきんきんしているのだが、その完全無欠なるジャジーなテクニックにはほとほと感心。 Brahms Prize  Bernard Haitink. London Symphony
Orchestra. Brahms: Symphonies Nos 1-4 etc. Bri. LSO Live Bernard Haitink. London Symphony
Orchestra. Brahms: Symphonies Nos 1-4 etc. Bri. LSO Live  現在の「巨匠」であられるHaitinkの三度目のブラームス全集で、ライブ
のもの。昨今、オケ側が自主制作として方々からライブ録音が発売されているが、中でもこのLSOレーベルはDavisとHaitinkを中心にかなり良い
出来のものを多数プロデュースしている。また、常に「成熟」しているHaitinkの棒も益々その円熟度を増して、良い意味でのシンプルさ、真面目さを感
じることが出来る。オケ自体はそれほどスーパーなオケでもないし、録音自体もDSDを使用している割に、妙にせせこましいものだし、全集全てにわたり特別
に素晴らしい訳ではないのだが、現代のブラームスの一つのレフェレンスかもしれない・・・。中では、第二番、第三番が秀逸であろう。第一番はかなり肩透か
しを喰らうほどの「こじんまりした」演奏かもしれないのだが。思えば、全集と言う形では大よそ第二番に名演が多い。このHaitink盤、Kempeの
ミュンヒェン盤、Wand+NDRの第一回目のもの、アーベントロート盤(正規盤ではないのだが)、バルビローリ、カイルベルト、スィートナー、セルなど
など。 現在の「巨匠」であられるHaitinkの三度目のブラームス全集で、ライブ
のもの。昨今、オケ側が自主制作として方々からライブ録音が発売されているが、中でもこのLSOレーベルはDavisとHaitinkを中心にかなり良い
出来のものを多数プロデュースしている。また、常に「成熟」しているHaitinkの棒も益々その円熟度を増して、良い意味でのシンプルさ、真面目さを感
じることが出来る。オケ自体はそれほどスーパーなオケでもないし、録音自体もDSDを使用している割に、妙にせせこましいものだし、全集全てにわたり特別
に素晴らしい訳ではないのだが、現代のブラームスの一つのレフェレンスかもしれない・・・。中では、第二番、第三番が秀逸であろう。第一番はかなり肩透か
しを喰らうほどの「こじんまりした」演奏かもしれないのだが。思えば、全集と言う形では大よそ第二番に名演が多い。このHaitink盤、Kempeの
ミュンヒェン盤、Wand+NDRの第一回目のもの、アーベントロート盤(正規盤ではないのだが)、バルビローリ、カイルベルト、スィートナー、セルなど
など。尚、カップリングの『悲劇的序曲』は非常な名演。 購入時のコメントは (「偉大なる中庸」、「静的な美観」というのが誠に相応しい大名演。我々は既にブラームスの全集として数多くの演 奏を知っており、こらまでも、これからもその数は増えていくであろう。Haitinkは確か今までに二回全集をしているはずだが[BSOとの一回だ け?]、私は聴いてこなかった。しかし、この LSOとのライブは彼の芸術の総決算といってよいほどの高水準かつ、彼の芸術性及び曲に対する相性・また愛情を知らしめさせたというべきであろう。兎に 角、よく流れよく歌う。ブラームス独特のメランコリーや厭世観が淡々とした解釈の中に著しく輝いている。こういったものは、既に功なり名なりなした、いう なれば大人の人間がようやくにして達成できる技であろう。ふっくらとして、無抵抗にブラームス・ワールドへ誘う。 オケもよくHaitinkの指導についてきており、特に、第三番のようにまとめ方が難しい曲も難なく、更には指揮者の意図をよく勘案して一体化して音楽 している。LSOは決してスーパー・オーケストラではないし、Liveでのしょぼい、とも取れる管楽器などの扱いもあるのだが、それでも、何しろ全てが自 然体で無理を感じさせないのはやはり名匠Haitinkだからであろう。 録音もC.Davisのドヴォルジャークの時よりも自然にマッチしており好感が持てる響きである。全集としてザンデルリンクの旧盤、新盤、ボールトのも の、バルビローリのもの、クレンペラー、スィートナーーと並び優れた仕事であるといえる。) Bruckner Prize  Leon Botstein. London Philharmonic
Orchestra. Bruckner Symphony No.5 Schalk Edition (1894) USA Telarc Leon Botstein. London Philharmonic
Orchestra. Bruckner Symphony No.5 Schalk Edition (1894) USA Telarc  世に言うシャルク版、改竄版である。が、これはあくまでも、後世からの評価
で、当時はこれがデフォルトであったはず。ハースのみならずノーヴァク版からは正直言って想像も出来ないほどの改編、改竄が施されているが、当本人として
は良かれとし
て行った行為であるはず。 世に言うシャルク版、改竄版である。が、これはあくまでも、後世からの評価
で、当時はこれがデフォルトであったはず。ハースのみならずノーヴァク版からは正直言って想像も出来ないほどの改編、改竄が施されているが、当本人として
は良かれとし
て行った行為であるはず。で、第四楽章が傑作、いや珍品?でも、こういったWagner風味のブルックナーも悪くない。それどころか、コーダの二重フーガでのシンバルクラッシュ は結構カタルシスを感じてしまうのであった。 購入時のコメント。。。 (世にも不思 議な、いや奇妙な改竄版のシャルク版によるもの。こりゃ、殆どマーラーとヴァーグナーの衣を無理やりに着せられて、ダイエットを敢行しているかのようだ。 特に普段ならば、カタルシスを感じる第四楽章のダブル・フーガではどりふの爆笑編になった。今の学術的見地、更には真摯なブルックナーファンにはとても耐 えられない代物であるに違いないのだが、作曲家!シャルクのアレンジを冷静になって聞いて見ると案外うけるかも。因みにKnaのDeccaのVPOとのや つもシャルク版である。) (かつてはまった珍品、シャルク版によるブル5である。解説書を読んだらなかなか面白いのを発見。なぜ、ナチス 時代にハースがブルックナーのスコアを研究、発表したかというと、作曲家存命より、彼のスコアをユダヤ系の版元が発表したので、「純粋」ドイツ人であり、 ヒトラー自身が、同郷の作曲家、ならびに、ゲルマンの作曲家とみなしていたブルックナーを自己の文化政策の一環としてハースに依頼したようだ。ハースは戦 時中のこういった政権との音頭とりの一翼を担った為に、ブルックナー研究は以降は進まず、ノーヴァクがエディットしたのは有名である。尚、ブルックナー自 身はシャルクの版に納得できず、初演にも参加せず、存命中には聞かなかったようだ。ただ、全否定は出来ない、というか、ブルックナー自身もこの「改竄版」 に参加した形式があり、シャルクにアドヴァイスをした痕跡もあるからだ。) Mozart Prize 2006年はMozart Yearでした。  Ton Koopman The Amsterdam Baroque
Orchestra: Coronation Mass etc. Erato Ton Koopman The Amsterdam Baroque
Orchestra: Coronation Mass etc. Erato  生き生きとしていながらも、優しささえも感じさせる演奏。バッハで名演を繰り
広げたコープマンはモーツァルトの派手派手ミサ曲でもそれを遺憾なく発揮している。神聖さよりも、ハイドンのようなユーモアさを持ち合わせたこの曲は、そ
の豪華絢爛さだ、が後期の名曲であるハ短調大ミサ曲及び、レクイエムとMozartと共に三大ミサ曲である。後期の二つの「真面目さ」には及ぶはずもない
のだが、
アマデウスの若さ爆発が楽しめる。うきうきのりのりである。 生き生きとしていながらも、優しささえも感じさせる演奏。バッハで名演を繰り
広げたコープマンはモーツァルトの派手派手ミサ曲でもそれを遺憾なく発揮している。神聖さよりも、ハイドンのようなユーモアさを持ち合わせたこの曲は、そ
の豪華絢爛さだ、が後期の名曲であるハ短調大ミサ曲及び、レクイエムとMozartと共に三大ミサ曲である。後期の二つの「真面目さ」には及ぶはずもない
のだが、
アマデウスの若さ爆発が楽しめる。うきうきのりのりである。歌手ではやはりソプラノのBarbara Schlickが優秀。合唱もコープマンの音楽性に合致している。 カップリングも秀逸。Ave verum corpus、VesperaeとExsultate, Jubilateである。  Karl Böhm. Wiener Staatsoper. Don
Giovanni. Live in London. Archipel Karl Böhm. Wiener Staatsoper. Don
Giovanni. Live in London. Archipel  購入時のコメント (彼の数多い同曲の録音の中で、第一回目のもの。場所はロンドン。引越し公演でのライブであり、錚々たる面子を集 めたもの。いや、吃驚した。エレガントながら押し付けがましくない圧倒感があり、VPOの魅力を十二分に描写している。Don Giovanniはなんといっても名曲、名作だが、それ故に感動を与えるのはなかなかに困難である。 音も酷いものと覚悟していたが、それほど悪くはない。ロイヤル・アルバート・ホールでの録音で恐らく演奏会形式っぽい。オケよりも歌手に録音が集中され てはいるが、団子状態にならない。或る意味での分離加減がある。 ベームはコンサート指揮者としてはそれほど高く評価していないし、二流指揮者(一流ではない、という意味)だが、オペラのしかもライブのそれ、更に50 年代の働き盛りの時期のものはやはりどれも傾聴に値する。彼の同曲は他に4つあるようだが、この調子でいくとライブのそれはやはり凄そうだ。特に、VPO とのザルツブルクでの録音は是非きいてみたい(DG)。 歌手では当時の「ヴィーン・モーツァルト・アンサンブル」の百花繚乱。ユリナックのエルヴィーラが特に精細を特に放っている。この人の声は、ガラス細工 のように透明かつ、一種の温かみのあるもの。 ところどころ、カットがあるが、音楽を楽しめるのはやはり気持ちが良いものだ。  Joseph Keilberth. WDR Köln. La
Clemenza di Tito. Andromeda Joseph Keilberth. WDR Köln. La
Clemenza di Tito. Andromeda    親方Mozartの晩年のオペラ・セリアを振る、といったもの。カイルベルト
は巷間オペラではWagner及びR.Strauss振りとしてその名前をはせているが、意外にそれ以外のオペラでも素晴らしいものが多々ある。戦中時代
よりMozartだけではなく、Verdi、Pucciniまでやっているし、それが又素晴らしいできだ。 親方Mozartの晩年のオペラ・セリアを振る、といったもの。カイルベルト
は巷間オペラではWagner及びR.Strauss振りとしてその名前をはせているが、意外にそれ以外のオペラでも素晴らしいものが多々ある。戦中時代
よりMozartだけではなく、Verdi、Pucciniまでやっているし、それが又素晴らしいできだ。指揮者の力量を測るにはオペラの序曲で大体分かるが、ここでもそれはあてはまっており、テンポといい、強弱といい、流し方といい、まさに最高。更に、 伴奏だけに徹しがちのオケの指揮者もここでは、歌手の伴奏が最高なだけではなく、そのオケの存在感も十二分に発揮している。思えば、彼が生きた時代はある 意味オペラにとって良い時代であったかもしれない。即ち、歌手が中心の時代と指揮者がまずオペラでの中心になった現今との丁度中間地点に位置しているから だ、と思う。 歌手では、Sesto役のMalaniukと、Vitellia役のZadekが素晴らしく、タイトルロールのGeddaも良い。 正規盤ではないが、録音及びリマスターともども優秀。レチタティーヴォが無いのでやや間の抜けた感じもしないではないのだが。 購入時のコメント。 (レチタ ティーヴォがない。やや駄作の感が無いでもない、Mozartの最後のオペラをなんともいえないほど、地に足着いた解釈。というか、真面目な大将が大好き そうなオペラセリアを正攻法で抑えている。が、それだけではないのがカイルベルトの凄さ。彼はWagnerとは違うアプローチを行っており、Mozart の持つ一種の優美さ、典雅さを、真正ドイツから引き出しているのがまたしても凄い。恐るべしカイルベルト!) Verdi Prize  Carlo Maria Giulini. Philharmonia
Orchestra. Verdi: Messa da Requiem etc. EMI Carlo Maria Giulini. Philharmonia
Orchestra. Verdi: Messa da Requiem etc. EMI  死人も蘇生するであろう、度派手なレクイエムな代名詞であるヴェルディのは、
結構その派手さだけで売りがあるようで、ビューローがぼこぼこに非難していた覚えがある。 死人も蘇生するであろう、度派手なレクイエムな代名詞であるヴェルディのは、
結構その派手さだけで売りがあるようで、ビューローがぼこぼこに非難していた覚えがある。が、しかしここでのジュリーニ盤は(彼は他にも二度録音、BPOとのCD、NPOとの映像)ダイナミズム、派手さは勿論デフォルトとしてあるが、それ以 上に溢れんばかりの歌心と、神聖かつ敬虔なレクイエムとの部分がある故に、これが「今世紀の偉大な録音」の一つであるのは至極当然のことであろう。 最初の極小のピアニッシモ!からドラマが開始され、二重フーガの最後まで、緊張と曲への同感、のめりこみがひしひしと伝わってくる。最初聞いたときには 最後の方の余りの荘厳さに身が震えた覚えがある。 今までにいくつか同曲を聴いてきたが、其の中ではやはりフリッチャイのものとトスカニーニのものが、打ちのめされた。実家にはライナーのがあったが又聴 いてみたい気がする。 歌手では今年ーようやくー亡くなったシュヴァルツコップを筆頭に、ギャーロフが突き抜けている。アルトのルートヴィヒ、テノールのゲッダも勿論優れてい るし、合唱もピッツの捌きは流石である。 Wagner Prize  Joseph Keilberth. Orchester der
Bayreuther Festspiele. Wagner: Die Walküre. 1955. Ger. Walhall Joseph Keilberth. Orchester der
Bayreuther Festspiele. Wagner: Die Walküre. 1955. Ger. Walhall  Andre Cluytens. Orchester der Bayreuther
Festspiele. Wagner: Tannhäuser. 1955. Ger. Walhall Andre Cluytens. Orchester der Bayreuther
Festspiele. Wagner: Tannhäuser. 1955. Ger. Walhall   Hans
Knappertsbusch.
Orchester der Bayreuther Festspiele. Wagner: Der fliegende Holländer.
1955. Ger. Walhall Hans
Knappertsbusch.
Orchester der Bayreuther Festspiele. Wagner: Der fliegende Holländer.
1955. Ger. Walhall  Otmar
Suitner. Staatskapelle Berlin. Wagner: Lohengrin Höhepunkt. Ger. Berlin
Classics Otmar
Suitner. Staatskapelle Berlin. Wagner: Lohengrin Höhepunkt. Ger. Berlin
Classics  Suitnerによ
る正規盤による唯一のWager。しかも残念ながら抜粋版である。彼は隠れWagner指揮者でバイロイトにも出演したこともあるし、非正規盤ながら
Ring全曲とか、Parsifalまであるのだが、正規盤でしかも手兵のシュターツカペレ・ベルリーンによるWagnerは現在これしかない。
Wagnerのは他に、下記のコロの伴奏とか、合唱のアルバムしかないから、それだけで彼のWagner観を決定するには少々危険かもしれないのだが、こ
こに聞かれるWagnerはやはりスケールの大きい、と同時に門がとれて丸みを帯びた、奥行きのあるWagnerである。 Suitnerによ
る正規盤による唯一のWager。しかも残念ながら抜粋版である。彼は隠れWagner指揮者でバイロイトにも出演したこともあるし、非正規盤ながら
Ring全曲とか、Parsifalまであるのだが、正規盤でしかも手兵のシュターツカペレ・ベルリーンによるWagnerは現在これしかない。
Wagnerのは他に、下記のコロの伴奏とか、合唱のアルバムしかないから、それだけで彼のWagner観を決定するには少々危険かもしれないのだが、こ
こに聞かれるWagnerはやはりスケールの大きい、と同時に門がとれて丸みを帯びた、奥行きのあるWagnerである。Parsifalにも通じるLohengrinの神秘性とロマン性は十二分に存在し、一種亡羊としたうねりがあるのも聴き忘れてはならない。しかしこの うねりは歴代のWagner指揮者のそれとやや違う、即ちクナッパーツブッシュやらカイルベルトやら、各々もつ異なるうねりとも、一線を画し重厚さはあっ ても窮屈さは感じない、自然を感じる爽やかさであろうか? 特徴すべきはやはりオケの透明さとシンパシーを感じさせざるを得ない温かみである。 残念ながら歌手がそれほどピンと来ない。特にLohengrin役のMartin Ritzmannは声と演技に魅力が無くがっかり。録音はBerlin Classics特有のはったりの無い自然な音作りで好感が持てる。  Otmar
Suitner. Rune Kollo. Staatskapelle Berlin. Wagner Arias Ger. Berlin
Classics Otmar
Suitner. Rune Kollo. Staatskapelle Berlin. Wagner Arias Ger. Berlin
Classics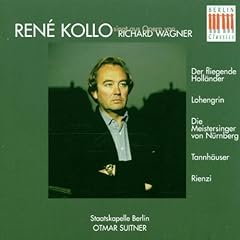   Kolloは
Suitnerとこの他にRingの「アリア集」を作っているが、そちらの方は聴いたことが無い。 Kolloは
Suitnerとこの他にRingの「アリア集」を作っているが、そちらの方は聴いたことが無い。上記のへぼ?Lohengrinを聞いた後にコロのを聞くとその違いが歴然であり、典型的な間抜けなテノールそのものだが、甘い声が聞こえてくる。リ リック・テノールであろうか?録音されたこの時代、即ち1972年はコロの全盛期だと思われ、多くの名盤を生み出しているし、やはり一人の素晴らしい Wagnerテノールの一人であることには間違いない。(個人的には偉大なWagnerテノールはWindgassenだけであるのだが・・・) ここでも、Suitner伴奏は、素晴らしく重厚さとまろみと、透明感が同時に表出されている。 録音も飛びぬけてよく、生々しいライブ感覚の音響がスピーカーから飛び出してくる。こりゃたまげた。 Opera Prize  Victor de Sabata. Teatro Alla
Scala. Rossini: Il Barbiere di Siviglia Ger. Walhall Victor de Sabata. Teatro Alla
Scala. Rossini: Il Barbiere di Siviglia Ger. Walhall  購入時のコメントは。。。 (嵐を呼ぶ 男、デ・サーバタ。その再度の感激・感度はなるか?CDをかけると直ぐに聞こえてくる、酷い音。かそけき雨模様の録音だ。が、このコメディーをまるで、 Wagnerみたいに・・・大袈裟かもしれないが・・・、煽動するのはやはり熱血漢デ・サーバタ。序曲から血管ぶっちぎれ、それでいながら、歌手 の邪魔をしていないし、バランスが良い。オケのスカラ座管も憑かれた様に弾いている。こんな、ロッシーニ聞いたことが無かった。音質を別にして、イタリア 原語版は今まで、ヴァルヴィーゾ、バルトレッティ、プレヴィターリしかしならなかったが、これからは、この演奏が「標準」になりそうだ。歌手では Rosina役のDora Gattaが最高だ。)  Heinz Wallberg Gürzenich-Orchester
Köln. Humperdinck: Hänsel und Gretel Ger. EMI Heinz Wallberg Gürzenich-Orchester
Köln. Humperdinck: Hänsel und Gretel Ger. EMI  最初の序曲から頬が緩みっぱなしになってしまうほど、気持ちが良いオーケスト
ラのコンディションと指揮者の解釈。これほどまでに立派な、そしてオーケストレーションをがっちり頑固に捌きながらも、曲の持つ夢見るようなロマンを出し
ているのは他にはなかなか見つからない。Suitnerのもなかなか良かったので、これはよい対抗馬といったところだし、あちらが旧東独のドレースデンで
あったのに対しこれは旧西独のケルンでの録音である。 最初の序曲から頬が緩みっぱなしになってしまうほど、気持ちが良いオーケスト
ラのコンディションと指揮者の解釈。これほどまでに立派な、そしてオーケストレーションをがっちり頑固に捌きながらも、曲の持つ夢見るようなロマンを出し
ているのは他にはなかなか見つからない。Suitnerのもなかなか良かったので、これはよい対抗馬といったところだし、あちらが旧東独のドレースデンで
あったのに対しこれは旧西独のケルンでの録音である。Suitnerを別として、Eichhorn、Rother、F.Lehmannを今までに聞いてきたが、これが一番しっくりくる。 EMIの録音もドイツ人がやれば、こんなにまともだという良い証左。 R.シュトラウスのようにフンパーディンクは天賦の才もないし、彼のようなドライで複雑なことが出来ないが、まぁ、チョコレートのようなRSといったと ころか? 天皇誕生日でもある、12/23に再聴したが、これは初演の日でもある。 父親役のPreyは大好きな歌手。でも、この役には余りにも立派過ぎて、Wagner的だ。勿論好意的な意味で、である。 以下は、ノートに載っていた、初演をヴァイマールで指揮したR.シュトラウスの作曲家へのコメント。 ... so echt deutsch ... "It is truly a masterpiece of the first rank. I haven't been so impressed for a long time. What refreshing humour, what delightful naive melodies! What artistry and refinement in the treatmen of the orchestra, what perfection on the overall form! What a wealth of invention, what magnificent polyphony, and all os original, so new and so genuinely German! My dear friend, you are a great master, and have given the German people a work that they scarcely deserve, but which one hopes they will soon appreciate as music of great importance." Old Recordings Prize  Rossini: Overtures & Bizet:
Carmen: Ferenc Fricsay, Rossini: Overtures & Bizet:
Carmen: Ferenc Fricsay,   購入時のコメント (これには驚 愕。ロッシーニの音楽が単なる、軽薄でどれも同じようなクレッシェンドだけのへぼいイタリア大量生産のものだとすると大間違い。一曲一曲、押し出しの強 い、ハンガリーの夜叉が一目散に切り刻むようなものだ。フン族の酋長が大陸を勢いよく制覇するかの感あり。しかも、ベルリンのオケを使用しているので、勿 論響きは非常に「ゲルマン的」なのだが、フリッチャイの同郷のライナー、セル、ショルティの相通ずるようなバーバリズムを基調とする音楽作りだ。正直、 ロッシーニの音楽でこれほどまでに傾聴したのは、トスカニーニとライナー以来だ。The Originalsの録音も非常に宜しい。) New Recordings Prize   同じ団体によるバッハのブランデンブルク協奏曲も実に爽やかで古楽器にあるような一種の「嫌味」がなくて爽やかな名演奏であった。 Re-Listening Prize  Brahms: Klavierkonzert Nr.2. Karl
Böhm, Wilhelm Backhaus Staatskapelle Dresden Jap. Shinseido Brahms: Klavierkonzert Nr.2. Karl
Böhm, Wilhelm Backhaus Staatskapelle Dresden Jap. Shinseido   今年はまった曲の一つに、ブラームスのピアノ協奏曲第二番があげられる。それ
を求め、いや、その吸引力をもっとも与えてくれたのがこの一枚。 今年はまった曲の一つに、ブラームスのピアノ協奏曲第二番があげられる。それ
を求め、いや、その吸引力をもっとも与えてくれたのがこの一枚。特に素晴らしいのが、第三楽章のチェロのソロ! "disappointed"
Price
因みにがっかり盤は  クリスティの
Mozart『魔笛』
Erato クリスティの
Mozart『魔笛』
Erato Mravinsky Leningrad
Philharmonic Orchestra: Tschaikowsky Symphonies Nos. 4-6, Stereo DG Mravinsky Leningrad
Philharmonic Orchestra: Tschaikowsky Symphonies Nos. 4-6, Stereo DG因みに、今年ある筋から頂いた、Altusのムラヴィンスキーのロシア音楽集大成の中に入っている、昔Melodiyaから出ていた1973年の第五番 は、演奏及びリマスターが最高に素晴らしく、これぞ、ムラチャイゴであるべし、と思った次第。 参 考文献 各種... |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
